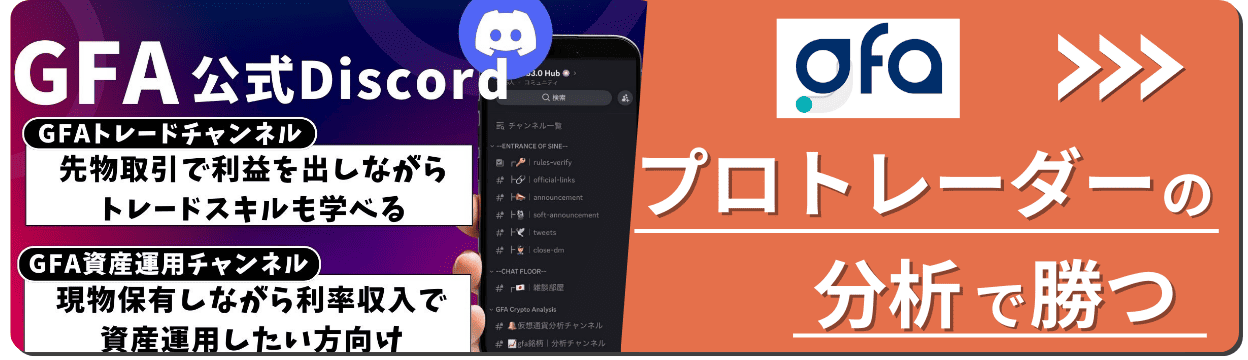ソラナベースのHeliumが通信大手AT&Tと提携、分散型無線ネットワークで1億人超にリーチ
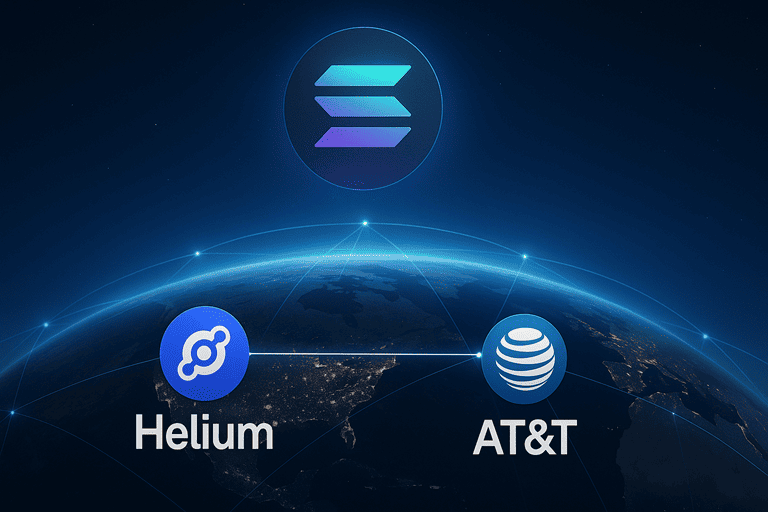
ソラナ(Solana)上で稼働する分散型無線ネットワークHelium(ヒリウム)は、米大手通信事業者AT&Tとの提携を発表した。この提携により、AT&Tの1億1,800万人超の加入者がHeliumのホットスポットを活用し、ネットワーク拡張の恩恵を受けることが可能となる。
通信大手との連携で「人々の力によるネットワーク」が拡大
Heliumは、個人や企業が運用するホットスポットによって構成された「人々の力で構築された分散型ネットワーク」である。ホットスポット運用者は、Heliumのソラナ基盤トークン(HNT)による報酬を受け取る仕組みとなっており、ユーザーがそのネットワークを通じてデバイス接続することで、さらなる報酬が発生する。
AT&Tとの提携では、同社加入者がHeliumネットワーク上のホットスポットに接続可能となり、エリアカバーの強化やユーザー体験の向上が期待される。また、AT&T側にはHeliumから「カバレッジ品質メトリクス」も提供され、データ品質の高度化も図られる。
Helium「実利用ベースでの普及が加速」、T-Mobileやテレフォニカとも提携
Heliumの共同創業者でありNova LabsのCEOであるアミール・ハリーム氏は、次のように述べた。
「AT&Tとの提携は、安価かつ誰でもアクセス可能な通信インフラを提供するという我々の使命にとって大きな前進である。業界を代表するパートナーとの連携により、Heliumの普及を一気に加速できる。」
Heliumは、既にメキシコにおいてテレフォニカ傘下のMovistarとも提携しており、2024年2月には230万人超のユーザーにHeliumネットワーク経由でモバイル通信サービスを提供。さらに、T-Mobileとの連携により5Gの補完インフラとしてHelium Mobileを展開している。
AT&Tとは
AT&Tは、アメリカ合衆国に本社を置く世界最大級の通信会社である。
創業は19世紀末にさかのぼり、長年にわたりアメリカ国内外で固定電話、モバイル通信、インターネット、テレビ放送などのインフラを提供してきた。モバイル部門では、米国内でVerizonに次ぐ規模を誇り、2024年末時点での加入者数は1億1,800万人を超える。
近年では、5G展開やIoT(モノのインターネット)分野への進出、そして今回のHeliumとの提携のような分散型インフラとの連携にも力を入れており、次世代通信プラットフォームの構築に向けた取り組みを強化している。
SEC訴訟も解決、トークンは証券に該当せずと明言
さらに注目すべき点として、Heliumの親会社Nova Labsが米SEC(証券取引委員会)との法的係争において勝利し、「Heliumのトークンおよびホットスポットは証券には該当しない」との判断が示されたことも重要である。
これにより、規制面での不確実性が大きく後退し、今後の展開に追い風となる見通しである。
GENAIの見解
 GENAI
GENAIHeliumとAT&Tの提携は、分散型インフラと従来型通信業界の架け橋となる非常に画期的な出来事であると考えています。
特に以下の3点で、その戦略的価値は極めて高いと評価できます。
まず第一に、分散型ネットワークが実際のモバイル通信サービスに統合される初の大規模な事例である点です。HeliumのようなDePIN(分散型物理インフラネットワーク)はこれまで、ホビー的な展開やローカルユースが中心でしたが、AT&Tのような世界的通信企業と連携することで、1億人を超えるモバイルユーザーが即座に接続可能となる実用的なユースケースが示されました。これは、ブロックチェーンベースのインフラが社会的インフラとして本格的に認められつつある兆候です。
次に、AT&TがHeliumから提供されるカバレッジ品質メトリクスを導入することで、単なるデータ中継ネットワークとしてではなく、通信効率やユーザー体験の向上にも寄与する高度なシステムとして評価されている点が挙げられます。これは、ブロックチェーンとAIによるネットワーク最適化といった未来型通信基盤の一端を担う可能性も秘めています。
最後に、米国証券取引委員会(SEC)がHeliumのトークンやホットスポットについて証券に該当しないとの見解を示したことは、今後の企業間連携や投資環境の安定化にとって非常に大きな後押しになります。規制リスクが後退したこのタイミングでのAT&Tとの提携は、事業展開を加速させる上で非常に戦略的です。
総合的に見て、今回の提携はHeliumにとってマーケティング以上の意味を持ちます。これは、分散型無線ネットワークが既存の通信インフラと融合し、次世代の通信モデルを形成していく第一歩と位置づけることができます。
今後は、他の通信キャリアやスマートシティ関連事業者との連携も期待され、分散型通信の本格普及が始まる転換点になる可能性が高いです。