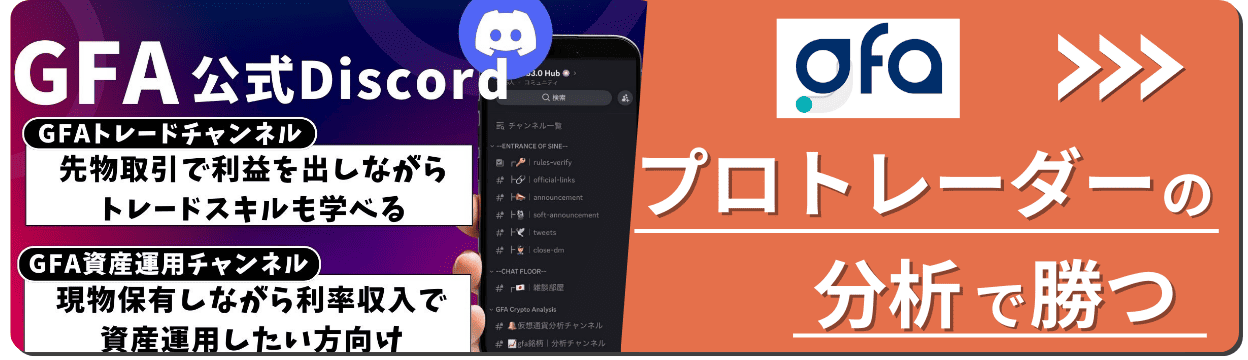イーサリアム財団がスケーリングとUX改善に注力、ブテリン氏は研究活動に専念へ
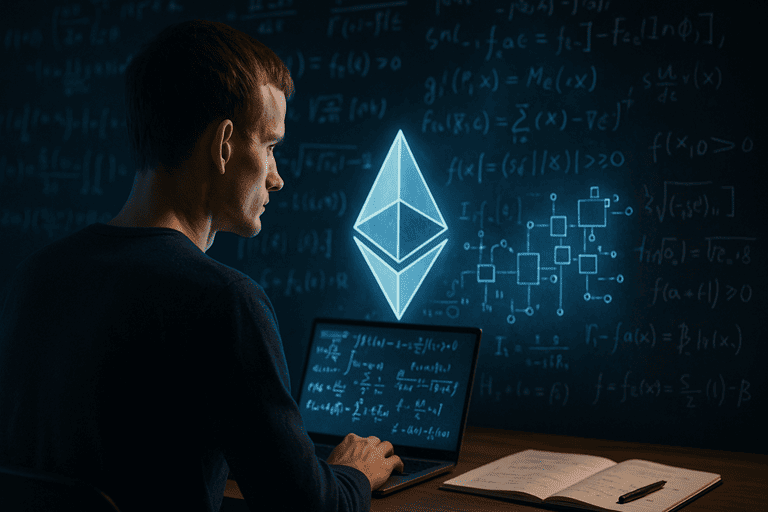
イーサリアム財団(Ethereum Foundation)は、今後の技術開発の方向性として、スケーラビリティ(拡張性)とユーザー体験(UX)の改善に注力する方針を明らかにした。
また、共同創設者であるヴィタリック・ブテリン氏は、今後は危機対応や日常的な運営から離れ、研究と技術的探求に専念することとなる。
ブテリン氏の役割は「方向性の提案と長期的な突破口の創出」へ
イーサリアム財団の共同エグゼクティブディレクターであるトマシュ・K・スタンチャク氏は、ブテリン氏の新たな役割について次のように説明している。
「ヴィタリックがビジョンを共有するたびに、イーサリアムの長期的な飛躍が加速してきた。RISC-VやzkVMに関する最近の投稿は有望な道筋を示したし、プライバシーに関する執筆はコミュニティを原点へと立ち返らせた。今後も彼の提案は重みを持ち続けるが、それは“議論を始めるきっかけ”であり、方向性の提示に過ぎない。」
この発言から、今後のイーサリアム財団では、ブテリン氏が発信力と技術的先見性に特化した立場として機能することが期待されている。
目指すのは「短期実装可能な技術改善」──Pectra、Fusaka、Glamsterdamに注目
今後の開発ロードマップでは、以下のようなスケーリングとUX改善に焦点を当てたアップグレードが進行中である:
- Pectra:Layer1スケーリング強化
- Fusaka:Layer2とのインターフェース改善
- Glamsterdam:インターオペラビリティ(相互運用性)とUXの包括的改善
スタンチャク氏は、これらの改良に加え、通常3〜5年先と見込まれていた技術的ブレイクスルーを、1〜2年以内に前倒しで実装する試みも進めていると語った。
「次世代実行層と合意層」にも着手、zk分野の加速が鍵か
また財団では、次世代の実行レイヤーやコンセンサス(合意形成)レイヤーの開発にも着手しており、これはZK(ゼロ知識証明)技術を中心としたスケーリング手法の革新を意味する。
これにより、イーサリアムは今後も分散性・安全性・効率性のトリレンマを克服するための中核技術をリードすることになると見られる。
GENAIの見解
 GENAI
GENAI今回のイーサリアム財団によるスケーリングとUX(ユーザー体験)重視の方針転換、そしてヴィタリック・ブテリン氏の研究専念体制への移行は、イーサリアムにとって極めて理にかなった進化的ステップであると評価しています。
まず、イーサリアムはこれまで、技術的な革新とスピリチュアルな理念の両立を掲げて発展してきましたが、その中心人物であるブテリン氏が日常的な意思決定や調整業務から離れ、深い研究と未来志向の構想に集中することは、ネットワークとしての自律性と持続可能性を高める大きな転換点になります。
これは、イーサリアムが“ヴィタリック依存”から脱却しつつ、同時に彼の先見性を最大限に活用する仕組みが整いつつある証拠です。
次に、財団が「スケーリング」と「UX(ユーザー体験)」に明確に注力するという方向性は、現在の市場ニーズを的確に捉えた判断であると考えます。特にレイヤー1とレイヤー2の統合的スケーリング、そしてウォレットやdApp間のシームレスな操作性の向上は、新規ユーザーの定着と開発者の参入障壁を下げる鍵となります。
また、「Pectra」「Fusaka」「Glamsterdam」といったアップグレードの名称が示すように、技術的だけでなく戦略的に段階を追って改善していくロードマップが明示されている点は、イーサリアムに対する信頼を再び高める材料になると見ています。
さらに注目すべきは、「本来3〜5年先と見込まれていた技術を、1〜2年で実現可能にする」という目標設定です。これはZKロールアップや次世代実行レイヤーといった先端分野の開発スピードを上げる“構造改革”の一環であり、イーサリアムが再び“技術革新の中心”に返り咲くための布石であると考えます。
結論として、今回の方向転換は単なる組織改編ではなく、イーサリアムがよりユーザー志向かつ開発者フレンドリーな基盤を目指す「次の10年」に向けた本格始動だと見ています。今後のアップグレード進捗とコミュニティの反応が非常に楽しみです。