
仮想通貨SUI(スイ)とは?将来性や新たなレイヤー1チェーンに注目が集まる理由を解説!
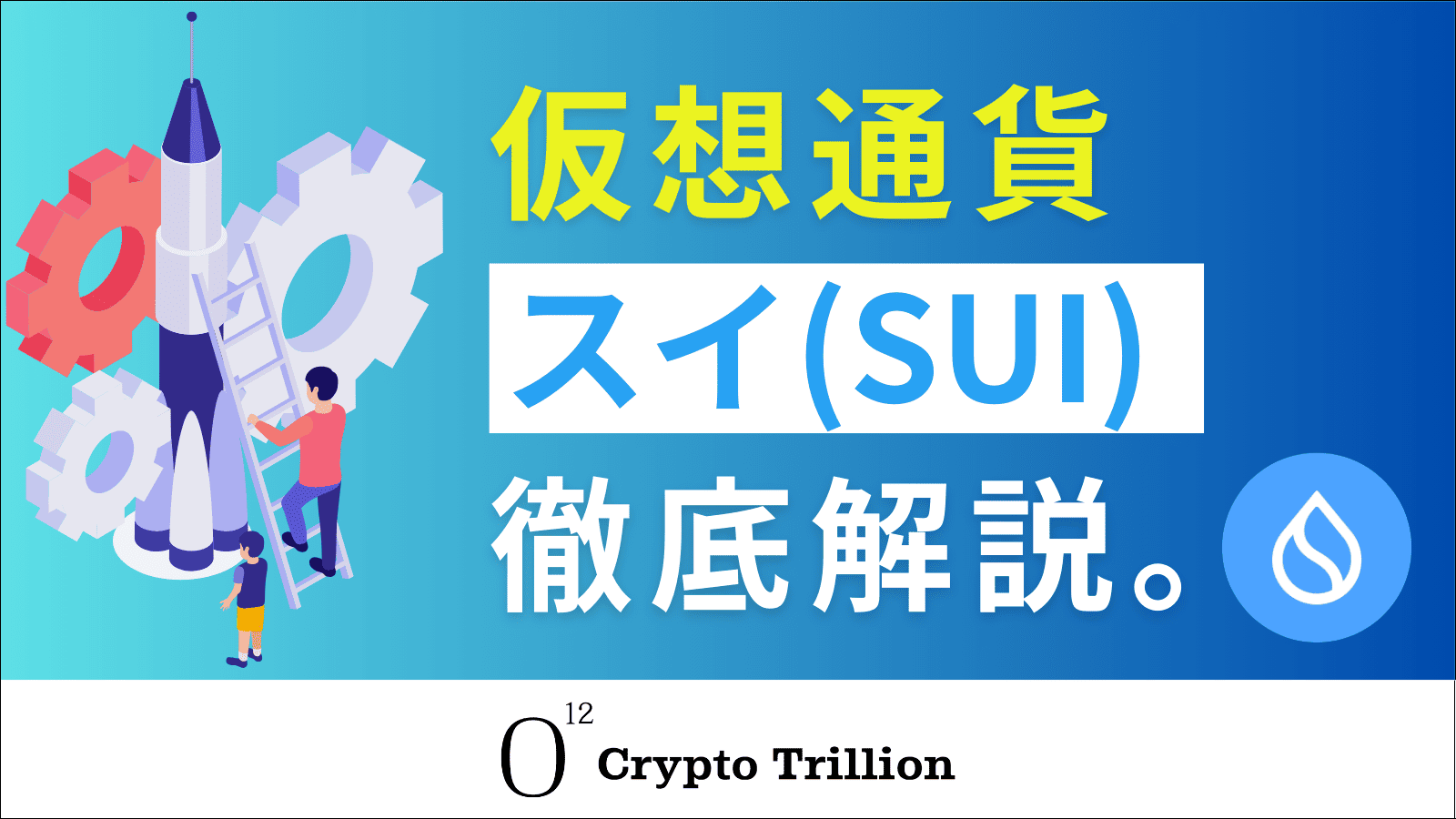
プロトレーダー トレーダーZのイチ押しポイント!
- SUI(スイ)は、スケーラビリティ問題の新たな解決方法を提示したレイヤー1ブロックチェーン
- 元々Meta社にいたDiem(Libra)のエンジニアたちが設立したチーム
- 各NFTや暗号資産を独立したノードで運用するため、ガス代が安く、トランザクション速度が速い
- サイドチェーンやレイヤー2のチェーンが注目される中、レイヤー1で人気を博している
- 仮想通貨SUIは海外の仮想通貨取引所に主に上場している
- 国内ではOKCoin JapanとBinance Japanに上場しているが、流動性的に海外での購入がおすすめ
- GMOコインやSBI VCトレードなどの送金手数料が無料の取引所を活用するとお得
 Trader Z
Trader Zスケーラビリティ問題を解決する方法の一つとして、サイドチェーンやレイヤー2のブロックチェーンである「Polygon」や「ライトニングネットワーク」などに頼っていましたが、SUIが出てきたことでそれが変化しつつあります。



SolanaやAvalancheもありますが、アップデートでネットワークが停止してしまったり、セキュリティの面で心配の声が上がっています。
そこでSUIは新しい仕組みを提供することで、レイヤー1のブロックチェーンとして地位を築いています。
\日本円の入出金・仮想通貨の送金手数料無料!/


Trader Z
ディーリングアドバイザー
世界第3位の仮想通貨取引所であるMEXCのトレーダーランキングにおいて、常に上位にランキングされる世界有数のトレーダー。
2024年10月には1,229,864,919.71USDT(日本円に換算して 1920 億円)の取引を行い、第1位となる。2024年12月にGFA Capital社が行う暗号資産ディーリング業務のアドバイザーに就任。


監修 Trader Z
ディーリングアドバイザー
世界第3位の仮想通貨取引所であるMEXCのトレーダーランキングにおいて、常に上位にランキングされる世界有数のトレーダー。
2024年10月には1,229,864,919.71USDT(日本円に換算して 1920 億円)の取引を行い、第1位となる。2024年12月にGFA Capital社が行う暗号資産ディーリング業務のアドバイザーに就任。
SUI(スイ)とは?
SUI(スイ)の概要
SUIはMysten Labsという企業が中心となって開発を進めています。
Mysten LabsはMeta社の暗号資産プロジェクト「Diem」(旧Libra)で核心技術を担当していたエンジニアたちが設立したチームです。
Diemそのものは当局の規制強化などによって頓挫しましたが、その経験値を引き継いでスタートしたのがSUIです。
ブロックチェーン業界には、すでにEthereumをはじめとする数多くのプロジェクトが存在します。
しかし、トランザクション処理速度やガス代の高騰といったスケーラビリティ問題を抱えることが多いとされています。
SUIはこれらの問題を根本から解決するために、独自のアーキテクチャを採用している点が注目ポイントです。
高速かつ安全なトランザクション処理を提供することを目的としており、Diem開発陣の知見が大きく反映されていると言えるでしょう。
SUIトークンの基本情報
SUIネットワークのネイティブトークンとして発行されているのがSUIトークンです。
ブロックチェーン上でのガス代やステーキング報酬、さらには将来的なガバナンス投票など、さまざまな用途に使われる重要な存在となっています。
発行量には上限が設けられており、ネットワークのセキュリティや分散性を支える基盤にもなるため、多くの投資家やトレーダーがその動向に関心を寄せています。
SUI(スイ)の特徴
Move言語と安全性
SUIでは、Diemから生まれたMoveという言語でスマートコントラクトを作成します。
資産を所有権という形で厳密に定義できるため、ハッキングや改ざんのリスクを抑えやすい設計が特徴です。
たとえばEthereumのSolidityでは管理が難しいコード部分が狙われる恐れがありますが、Moveはユーザーごとの資産を「個別のボックス」に分けたうえで、それぞれ誰が何を操作できるかを明確に定めます。
その結果、他人のボックスを勝手にいじる行為を防止しやすくなるのです。
さらに、NFTやトークンを独立したオブジェクトとして扱えるため、互いに影響し合わない取引は同時並行で処理できます。
たとえばAliceが持つNFT Aの売買と、Bobが持つNFT Bの送金は、どちらも所有者とデータがまったく別なので、ネットワークが両方の取引を同時に進めても衝突しづらい仕組みです。
Ethereumなど多くの従来型ブロックチェーンでは、トークンをひとつの大きな口座にまとめて管理する構造が中心のため、全取引を直列で実行する必要があるケースが多く見られます。
これに対しSUIのように資産を個々のオブジェクトとして扱うと、データの所有権が重ならない限りは独立した処理と見なせるため、結果として混雑しにくい高速トランザクションを実現しやすいのです。
こうした仕組みがSUIの高いセキュリティとパフォーマンスに大きく関わっていると言えるでしょう。
高いスループットと拡張性
SUIは、並列処理と独自のアルゴリズムを組み合わせることで、高速コンセンサスを可能にしています。
一般的なブロックチェーンが全トランザクションを一括合意するのに対し、SUIはMove言語の特性を活かし、干渉しない取引を一気に同時処理する設計です。
倉庫を複数の通路に分けるイメージで、それぞれの通路が別々の資産を動かしても衝突しにくくしています。
また、単純な送金は軽い手順で承認し、問題のある取引だけを重点的に検証する方式を採用しているため、ネットワーク全体の効率が向上しやすいのです。
将来的には水平スケーリングにも対応するとされ、バリデータの増加に伴って処理能力を拡張できる見通しです。
さらに、サイドチェーンやブリッジを整えることで、他のブロックチェーンから資産を持ち込みやすい環境づくりが進められています。
低手数料と独自のガス設計
SUIは、トランザクション手数料をなるべく抑えることを目指し、ユニークなガス設計を導入しています。
大きな特徴として、ブロックチェーン上に保存するデータ量に応じてコストが決まる仕組みを一部採用している点が挙げられます。
不要になったデータを削除すると手数料が返還される可能性がある仕組みも検討されているため、ユーザーは過剰なデータを残さずに済むモチベーションが働くと考えられます。
高速かつ安価に取引できる環境が整えば、ゲームやNFT分野など多様な分野での利用が期待できるでしょう。
SUI(スイ)が有名になった理由
Meta(Facebook)のDiemプロジェクトとの関係
SUI最大の話題性の源になっているのが、Meta(当時はFacebook)のDiemプロジェクトに関わっていたメンバーが主要なポジションを担っている点です。
Diemは大規模SNSと連携する新しいデジタル通貨として世間の注目を集めましたが、結果的に規制問題などで計画が中止となりました。
そこで得た知識や技術をSUIに転用する形となり、「MetaのDNAが受け継がれた次世代チェーン」という評価が早い段階から根付いています。
大型投資家と主要取引所の注目
SUIは、メインネット開始前から複数の大型投資家による資金調達を成功させました。
投資家の中には暗号資産業界で名高いベンチャーファンドや取引所が含まれており、将来的な成長を見込んで早期から資本が集まった形です。
さらに、Suiのメインネット開始に合わせて、Binance、OKX、Huobi、Upbitなど世界の主要暗号資産取引所が一斉にSUIトークンの上場を発表・実施ししたことが、大きな話題を呼びました。
複数の取引所がほぼ同時にSUIの上場を発表し、多くのユーザーが売買に参加する流れが生まれたため、SUIの名前が一気に世界へ広まったと考えられます。
SUI(スイ)の今後・将来性
ロードマップとエコシステム拡大
SUIの公式ドキュメントでは、さらなるパフォーマンス向上や新機能の実装が計画されていると示唆されています。
具体的には、Move言語の改良やネットワークの分散性を高めるための取り組みが進められる方針です。
DeFiやNFTだけでなく、ゲームやメタバースなど多様な分野での利用が想定されているとアナウンスされており、今後はより多くのプロジェクトがSUI上で開発されていくかもしれません。
このようにエコシステムが拡大すると、ユーザーや投資家の関心が高まると考えられています。
高速処理で不便が少なく、手数料も安く抑えられる可能性がある点は、既存のブロックチェーンが抱える課題を克服しうる利点となりそうです。
専門家の評価と市場の展望
SUIは既存のレイヤー1チェーンと比較しても高い処理能力が見込まれるため、専門家からは今後の成長に期待する声が聞かれます。
しかし、すでに幅広いエコシステムを形成しているEthereumなどのプラットフォームと比べると、ネットワークの成熟度や分散化の度合いにおいて課題が残されているとも言われています。
実際のところはロードマップ通りに技術開発やコミュニティ形成を進められるかが重要なポイントになるでしょう。
市場の動向は暗号資産全体の相場にも左右されるため、一概にSUIのみが上昇するとは限りません。
とはいえ、インフラとしての完成度が上がれば、大型企業や機関投資家との連携が拡大する可能性もあります。
こうした動きが具体化すれば、SUIの存在感はさらに高まるのではないでしょうか。
他の仮想通貨との違い
Ethereumとの比較
SUIとEthereumでは、コンセンサス方式やスマートコントラクト言語が異なります。
EthereumではGas代の高騰が課題になるときがありますが、SUIはネットワークレベルで並列処理を設計しているため、混雑が起こりにくいとされています。
Ethereumは多くの開発者コミュニティや実績を持つ点でリードしていますが、SUIはオブジェクトベースのデータ管理やMove言語の優位性をアピールしており、その差別化によって独自のポジションを築こうとしている印象です。
Solanaとの比較
Solanaも高速処理を特長とするチェーンですが、SUIはより並列処理の仕組みを重視している点で異なる性格を持ちます。
Solanaは大規模な負荷時にネットワークが一時停止する事例があったことが知られていますが、SUIはオブジェクトごとに取引を完結させられるとされ、ネットワーク全体が止まるリスクを減らす方向へ舵を切っています。
Suiでは単純なトークン送金に全ノードの合意を必要としない一方、Solanaでは各取引をグローバルに順序付けする必要があります。このアプローチの違いから、Solanaは高速ながらも混雑時にリーダーノード周りでボトルネックが発生しやすく、一方Suiは混雑耐性に優れる可能性があります。
どちらも高性能を強みとしており、ゲームやDeFiなどリアルタイム性が求められる領域で人気を博す可能性があります。
AptosやAvalancheとの比較
AptosはSUIと同様にMove言語を採用しているため、しばしば比較対象になります。
両者ともDiem由来の技術を取り入れている点で共通していますが、SUIとはやはりオブジェクトベースの管理など細かな設計思想が異なります。
Avalancheはサブネットを活用することでスケーラビリティを図っていますが、SUIはレイヤー1そのものを強化しながら拡張していくアプローチをとります。
いずれのプロジェクトにも特有の長所と短所があり、今後の開発スピードと普及状況によって評価が変わっていくかもしれません。
SUI(スイ)に関するニュース・動向
新たな提携やアップデート情報
SUI財団やMysten Labsの公式発表によると、最近は大手ゲーム会社やDeFiプラットフォームとの連携が進んでいると報じられています。
NFTマーケットプレイスの導入例も増えてきたようで、SUIの高速処理がユーザーエクスペリエンス向上につながるとして期待が高まっています。
こうしたニュースが続くと、投資家や開発者の注目度がいっそう増していくでしょう。
アップデート情報としては、Move言語の新バージョンリリースやウォレット機能の改善が取り上げられています。
特に一般ユーザーがウォレット操作を簡単に行えるような仕組みが整うと、暗号資産に詳しくないユーザー層にもSUIが使いやすいと感じられる可能性があるのではないでしょうか。
価格動向・市場での反応
最近はETFに関連する話題や機関投資家からの追加出資が報じられたことで、SUIトークンの取引高が増加したと伝えられています。
価格が急騰するといったシーンも一部で見られましたが、同時に仮想通貨市場全体の変動も続いているため、上下に振れやすい状況が続いているようです。
今後は暗号資産全体の相場トレンドだけでなく、SUI固有の技術開発や企業との連携ニュースが価格変動の材料となる可能性が考えられます。
仮想通貨SUI(スイ)とは まとめ
SUI(スイ)は、MetaのDiemプロジェクトに携わったエンジニアたちが生み出した次世代ブロックチェーンとして注目を集めています。Move言語と並列処理の仕組みを活用することで、高速かつ安全なトランザクションを実現しようというアプローチが特徴です。
大型投資家からの支援と主要取引所での上場によって一躍有名になりましたが、ネットワークの成熟度や分散化の度合いをさらに高める必要があると指摘されることもあります。
EthereumやSolana、Aptosなど他のレイヤー1チェーンと比較すると、それぞれに異なる強みや課題があり、今後の競合や連携の行方が注目を集めそうです。最近ではゲーム会社との提携やDeFiの拡大など、エコシステム構築に向けた動きが続いています。
高い処理能力と低手数料を武器に、今後さらに利用範囲を広げていくかもしれません。
最新情報をチェックしながら、あくまでも個々の資金状況やリスク許容度を考慮した上でSUIの動きを見守っていくことが大切ではないでしょうか。

