
イールドファーミングとは?高利回りの裏に隠れたリスクやメリット、始め方まで徹底解説

プロトレーダー Trader Zのイチ押しポイント!
- イールドファーミングとは、DeFiに資産を預けるだけで高利回りを得られる運用方法
- 年利で数十%を超えるDeFiプロトコルがある。
- ただし、ハッキングや価格変動リスクなど、ハイリスクである点には注意が必要
- プールに資金を投入するだけのため、トレードスキルが必要ない
- ただし、投入している仮想通貨の価格変動によって原本割れする可能性があるため注意
- 長期保有前提で積み立てをしている場合、掛け合わせることで効率良い運用ができる
- イールドファーミングはリスク管理の意識が重要
- 複数のDeFiを利用して分散することでハッキングや詐欺のリスクを減らせる
- 価格が急騰しても、本来の値上がり益よりも低くなってしまうインパーマネントロスが発生する
 Trader Z
Trader Zイールドファーミングは、DeFiサマーと呼ばれるほどに、DeFiが有名になった要因の一つです!



プールに2つの通貨ペアを預けることで、流動性提供者となり、高利率の利回りを得ることができる運用方法です!
その反面ハッキングやインパーマネントロス、引き出しと預入に対する手数料の関係など、複雑な計算も含まれるため資産管理が難しいですが、銀行や金融機関からは得られないリターンがあるため人気を博しています!


Trader Z
ディーリングアドバイザー
世界第3位の仮想通貨取引所であるMEXCのトレーダーランキングにおいて、常に上位にランキングされる世界有数のトレーダー。
2024年10月には1,229,864,919.71USDT(日本円に換算して 1920 億円)の取引を行い、第1位となる。2024年12月にGFA Capital社が行う暗号資産ディーリング業務のアドバイザーに就任。


監修 Trader Z
ディーリングアドバイザー
世界第3位の仮想通貨取引所であるMEXCのトレーダーランキングにおいて、常に上位にランキングされる世界有数のトレーダー。
2024年10月には1,229,864,919.71USDT(日本円に換算して 1920 億円)の取引を行い、第1位となる。2024年12月にGFA Capital社が行う暗号資産ディーリング業務のアドバイザーに就任。
イールドファーミングとは?


- DeFiの仕組みを使い、仮想通貨を預けることで高い利回りを狙える投資手法
- 中央管理者を介さず、スマートコントラクトによって自動で運用が行われる
- 年利が数十%を超えることもあり魅力的だが、その分リスクも大きい
- 2020年ごろからブームが起こり、現在も注目が続いている
イールドファーミングは、銀行預金とは比べ物にならないほど高い利回りを得られる可能性がある運用方法です。仮想通貨を貸し出したり、分散型取引所(DEX)の流動性プールに預けたりすると、取引手数料や利息、さらには独自トークンなどが報酬として配分される仕組みになっています。
「銀行預金の金利では物足りないけれど、仮想通貨をうまく活用すれば一発逆転できるかもしれない」と考えている人がイールドファーミングに興味を抱くことは多いです。
ただし、仕組みやリスクを正しく理解しないまま参入すると、資産を大きく減らすリスクもあるため注意が必要です。
イールドファーミングの定義
イールドファーミングとは、暗号資産を特定のDeFi(分散型金融)サービスに預け入れ、その対価として報酬を受け取る投資スタイルです。
銀行とは異なり、中央管理者が存在せず、ブロックチェーン上のスマートコントラクトというプログラムで利息や手数料が自動分配されます。
従来の金融システムでは、預けた資金は銀行や証券会社といった組織が管理していました。
しかし、イールドファーミングの場合は、預け入れと同時に誰でも貸し手・流動性提供者になれる点が特徴です。
イールドファーミングが注目を集める理由
2020年に「Compound」というレンディングプラットフォームが独自トークン「COMP」をユーザーに報酬として配布したことで、イールドファーミングが一気に注目されました。
仮想通貨を預けるだけでトークンがもらえ、しかもそのトークンが値上がりすれば大きな利益につながるため、多くの投資家が参加しました。
その後、数多くのDeFiプロジェクトが「独自トークンの配布」や「高い年利の提供」を競い合うように始め、イールドファーミングはハイリスクながらハイリターンを狙える投資として大きな話題になりました。
現在でもリスクを許容できる人々にとっては魅力的な選択肢といえます。
イールドファーミングの特徴と仕組み
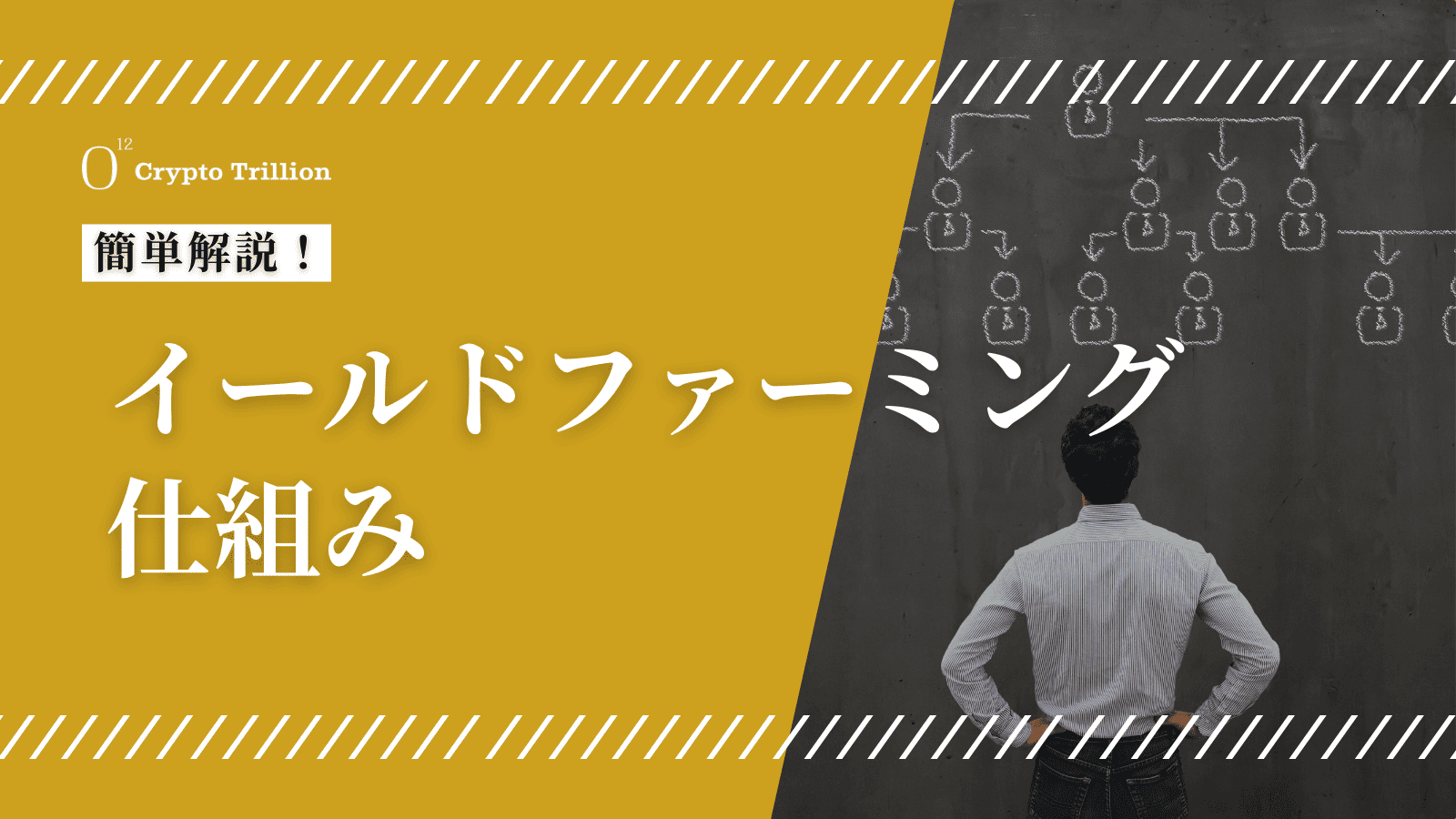
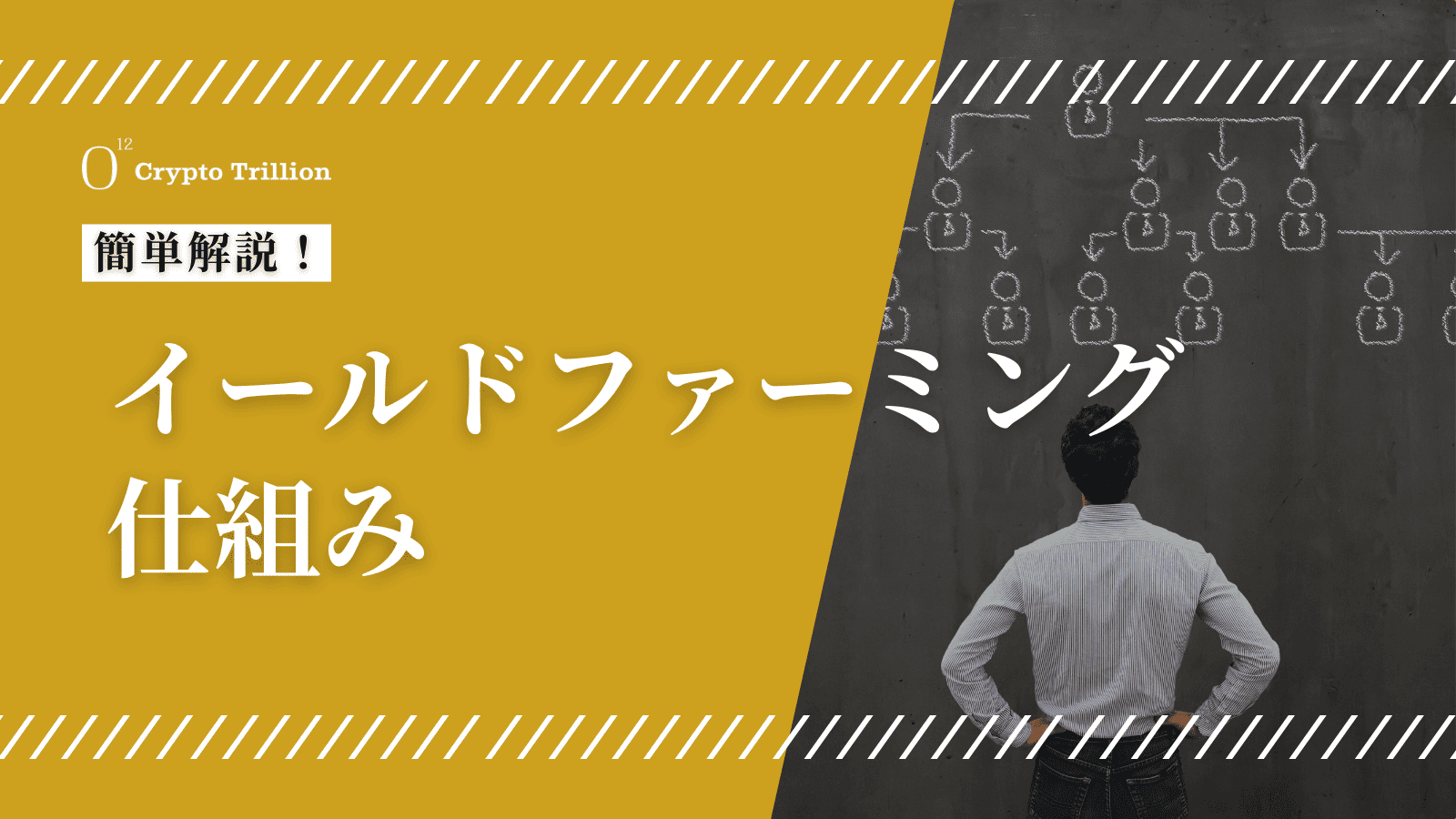
- 銀行のように中央集権的な管理者が不在
- スマートコントラクトによって運用が自動化されている
- 流動性プールに複数の通貨を提供すると取引手数料などが分配される
- 報酬は通貨の価格変動やプロトコルの設計によって大きく左右される
イールドファーミングの本質は「仮想通貨の保有者が貸し手や流動性提供者になり、その対価を受け取る」という仕組みにあります。
銀行の場合は、顧客が預金すると銀行がその資金を運用して利益を生み出し、預金者にはわずかな金利が支払われる形です。
しかし、イールドファーミングでは運営母体ではなく、ユーザー同士が直接お金を貸し借りしたり仮想通貨を交換したりするので、報酬配分の仕組みが分散化されています。
スマートコントラクトの役割
スマートコントラクトとは、ブロックチェーン上で動作する「条件が満たされると自動で実行されるプログラム」です。イールドファーミングでは、報酬計算や資金ロックなどをスマートコントラクトが制御します。
中央の管理者がいないかわりに、コードに書かれたルールがそのまま実行される仕組みです。
このおかげで、世界中の誰もが銀行口座を持たなくても、ウォレットひとつで簡単に仮想通貨の運用に参加できます。
しかし、プログラムのバグやハッキングが起きた場合には、多額の資金が一瞬で失われるリスクがある点も覚えておく必要があります。
流動性プールと流動性マイニング
分散型取引所(DEX)で活用される流動性プールとは、ユーザー同士が仮想通貨を交換できる「池」のような場所です。参加者は自分の仮想通貨をプールに提供することで、取引手数料の一部を報酬として受け取れます。これを「流動性マイニング」と呼ぶこともあります。
DeFiの分散型取引所(例えばUniswap)における資金プールで、ユーザーが異なる2種類の仮想通貨(ETHとUSDTなど)をペアで預けて作ります。
このプールが取引の相手先となり、ユーザーは直接相手を探さずに通貨を交換可能です。
交換レート(価格)はプール内のトークン残高比率で自動的に決まり、流動性提供者(LP)は取引のたびにかかる手数料の一部を報酬として受け取ります。
例えば、イーサリアム(ETH)とステーブルコイン(USDC)のペアを同額ずつプールに預けると、ユーザーがETHとUSDCを交換するたびに手数料が発生し、それがプール提供者に分配される仕組みです。
ただし、預け入れ中は2つの通貨の価格変動リスクを負うことになります。
報酬の計算と複雑さ
イールドファーミングの利回りは、年利換算で一時的に数百%やそれ以上に達することがある一方、短期間で急激に下がるケースもあります。
プロジェクト独自のトークンが値上がりすれば高い利回りを実現するかもしれませんが、その逆に下落すれば期待値を大きく割り込む可能性もあります。
また、報酬は複数の要素から成り立つため、正確に把握しづらい面があります。
受け取ったトークンの価格変動や、プラットフォームの利用者数の増減による手数料収益の上下など、さまざまな要因を考慮しなければなりません。
例えば、1トークン100円のAトークンをイールドファーミングで増やすとします。1年の利回りが100%としても、1年後のAトークンの価格が1円ならば、1年経っても2円にしかなりません。
こういった価格変動リスクを踏まえる必要があるため、なるべく価格の安定した仮想通貨で行うことをおすすめします。
イールドファーミングのメリット


- 銀行預金や国債に比べて圧倒的に高い利回りを期待できる
- 仮想通貨を有効活用して、売却益と合わせた複利運用を狙える
- 一度預けると基本的に自動で報酬が発生するため、手間が少ない
- DeFiエコシステム全体の拡大に乗って、新しい収益機会が増える可能性がある
イールドファーミングの一番の魅力は、大きなリターンを得られる可能性があることです。
特に、長期で保有しようと思っていた仮想通貨を使いながら追加で利息や手数料報酬を得られるため、「ただ持っているだけより断然お得」と感じる投資家は多いです。
「もう少し積極的に運用したいけれど、取引のタイミングを計るトレードは自信がない」という方には、資産をプールに入れて自動で報酬を得る仕組みは親和性が高いといえます。
パッシブインカムの獲得
パッシブインカムとは、積極的な取引を行わなくても定期的に収益が得られる仕組みのことです。
イールドファーミングでは、資産を預け入れることで自動的に報酬が獲得できるため、常に市場を監視する必要はありません。
そのため、日々の仕事で忙しい人でも比較的始めやすい方法といえるでしょう。
ただし、市場が大きく変動した場合には、資産価値の下落リスクが高まるため、定期的なチェックや適切なメンテナンスを怠ると予想外の損失につながることもあります。
保有通貨の有効活用
すでにイーサリアムやビットコインなどを保有している場合は、それらをただウォレットに眠らせておくよりもイールドファーミングで増やしたいと考える方が少なくありません。
売却をしないまま利回りを得ることで、長期投資と短期的な利益追求を同時に行える可能性があります。
とはいえ、複数の通貨をペアで預ける場合はインパーマネントロスがつきまといますし、預け入れ先のプラットフォームが安全である保証はありません。
高い利回りに目を奪われず、仕組みやリスクをきちんと理解したうえで検討することが大切です。
イールドファーミングのデメリット・リスク
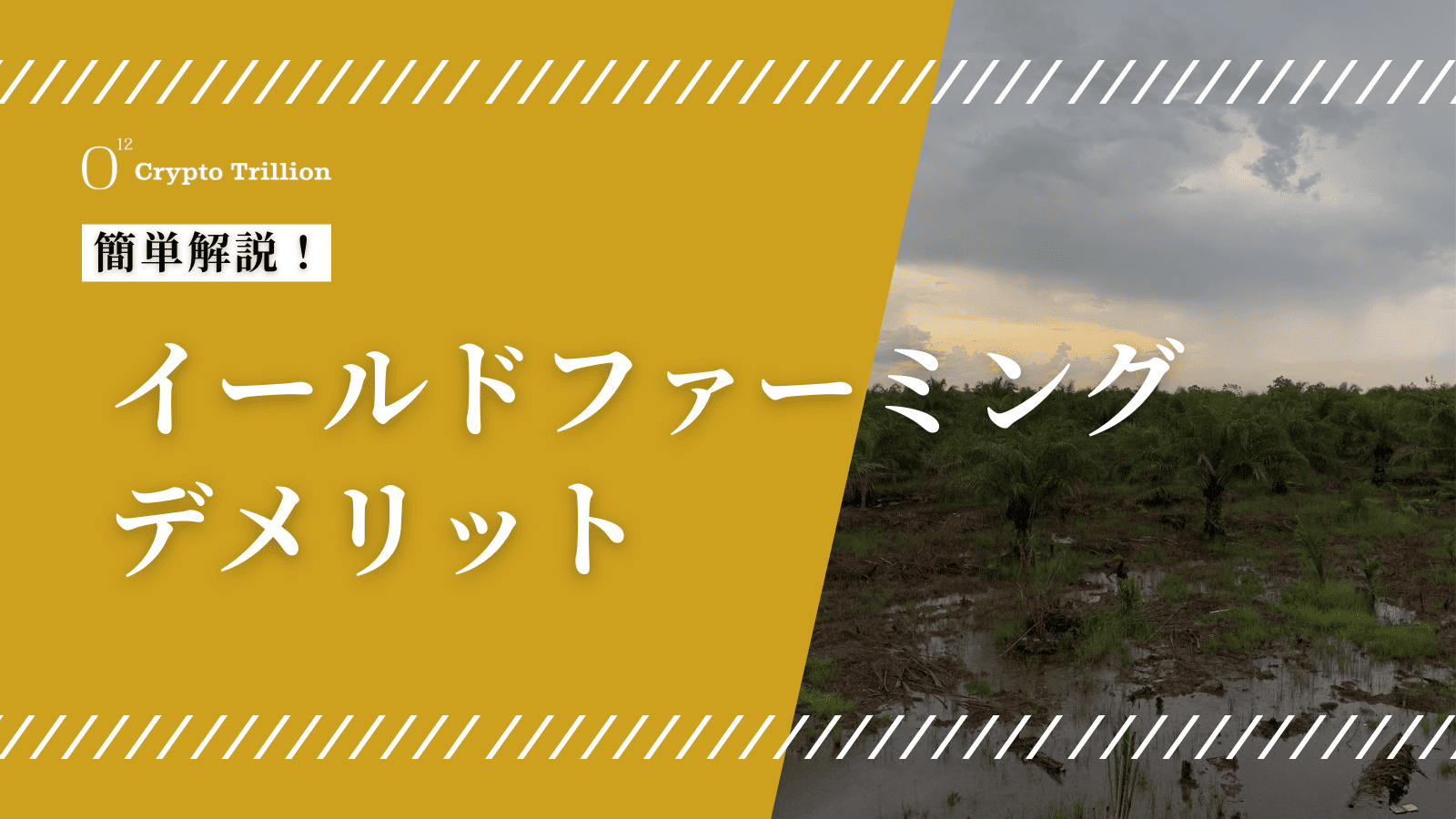
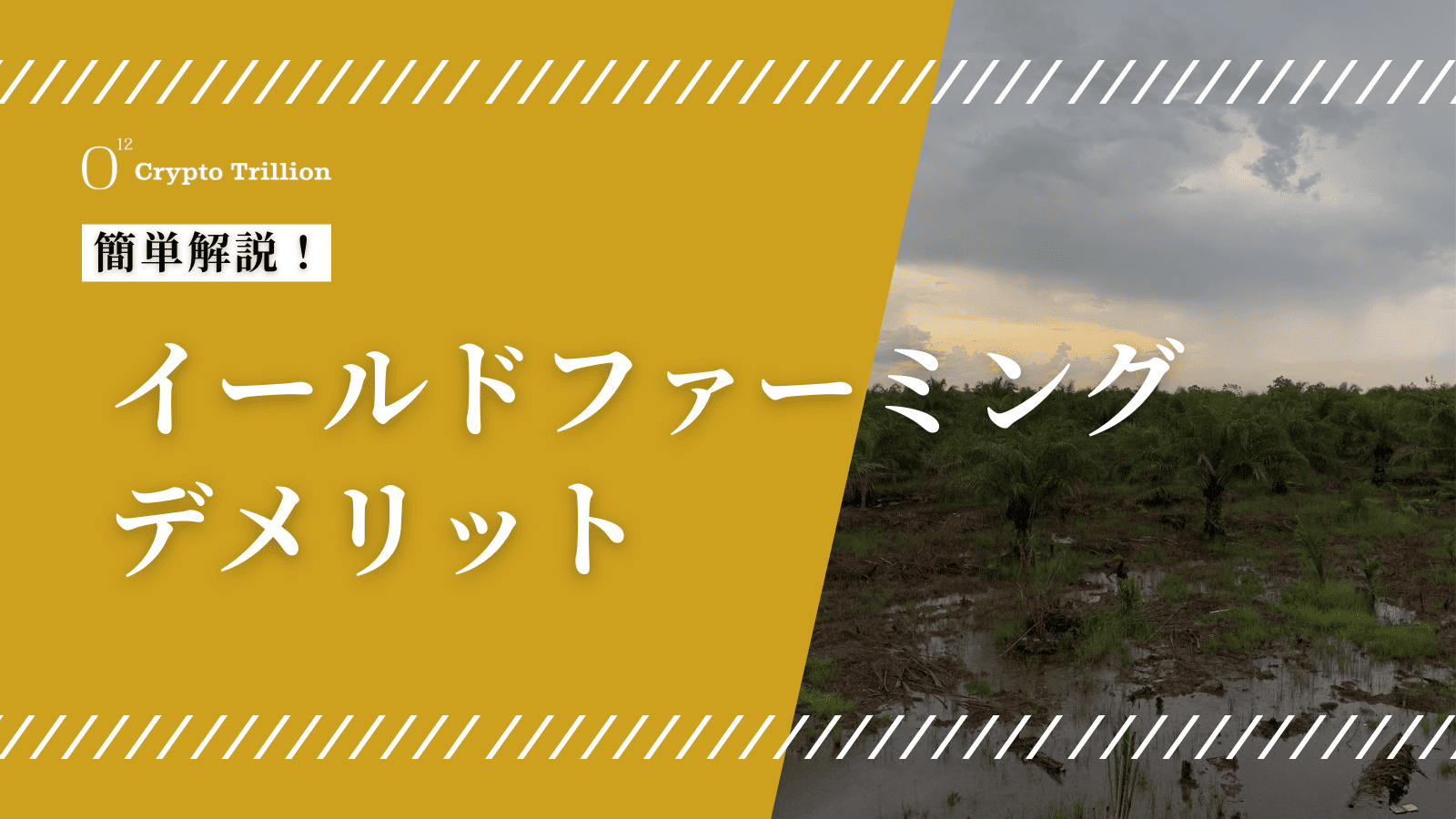
- 仮想通貨の価格下落で元本割れするリスクが高い
- インパーマネントロスによって、思ったよりも利益が残らない可能性がある
- ハッキングやバグで資金が盗まれる(ロック)されるリスクが存在する
- ガス代やシステム手数料が高騰して、報酬を上回るコストになる場合がある
イールドファーミングには大きなリターンを期待できる一方、それに見合うだけのリスクも存在します。
特に「価格変動」「インパーマネントロス」「ハッキングリスク」「手数料」などは、初心者がしっかり理解しておかないと、思わぬ損失につながる原因になります。
「少しの下落なら耐えられるし、やってみようかな」と考えている方にとっても、どのくらいリスクを取れるかを明確にしておかないと運用失敗時に大きな打撃を受ける可能性があります。
インパーマネントロスの注意点
流動性プールに二種類の通貨を預けると、価格が変動するたびにスマートコントラクトが自動的に通貨量を調整します。
その結果、もし一方の通貨が大幅に値上がりしても、プールでは高騰した通貨が自動的に売られ、値上がり益を十分に享受できない場合があります。
これを「インパーマネントロス(一時的損失)」と呼びます。
実際はプールから引き出す際に初めて損が確定するため、引き出すタイミングが重要です。
しかし、急激な価格変動の真っ只中で慌てて引き出すと、予想外に大きな損失を確定させてしまうこともあります。
ハッキングやバグのリスク
DeFiプロジェクトはオープンソースで開発されていることが多く、誰でもコードを閲覧できます。
透明性が高い一方で、脆弱性を見つけた悪意あるハッカーが大量の資金を盗む事件も過去に何度か起きています。
また、コードのバグによって資金が動かなくなってしまうケースもゼロではありません。
監査を受けたプロジェクトでもリスクは存在するので、「大手だから安心」とは言い切れないのが現状です。
運用コストの問題
イーサリアムをはじめとするブロックチェーンでは、取引や契約実行のたびに「ガス代」がかかります。
ネットワークが混雑しているとガス代が高騰し、頻繁にプールに出し入れを行うだけで利益が圧迫される可能性があります。
手数料が安い他のチェーンを使う選択肢もありますが、その場合は大手ほどの流動性がなく、期待した報酬が得られないケースがあるかもしれません。
初心者の場合は、コスト面まで計算してから本格的に資金を投入するようにすると安心です。
イールドファーミングの始め方


- 国内外の取引所で仮想通貨を購入し、メタマスクなどのウォレットを用意します
- DeFiプラットフォームにアクセスし、流動性プールやレンディングに資金を預けます
- 報酬を随時受け取りながら、必要に応じて解除や利益確定を行います
イールドファーミングを始めるためには、まずウォレット(MetaMaskなど)と取引所の口座を用意し、仮想通貨を購入します。購入した通貨をウォレットへ送金し、目的のDeFiサービスに接続して預け入れると、報酬が発生し始めます。
始めたばかりの頃は送金や承認の手順に戸惑うかもしれませんが、一度慣れるとそれほど難しい作業ではありません。
ただし、慌てて操作すると資金を間違ったアドレスに送ってしまうなどのミスが起こりやすいので、最初は必ず少額でテストするのがおすすめです。
イールドファーミングの最新ニュース・動向
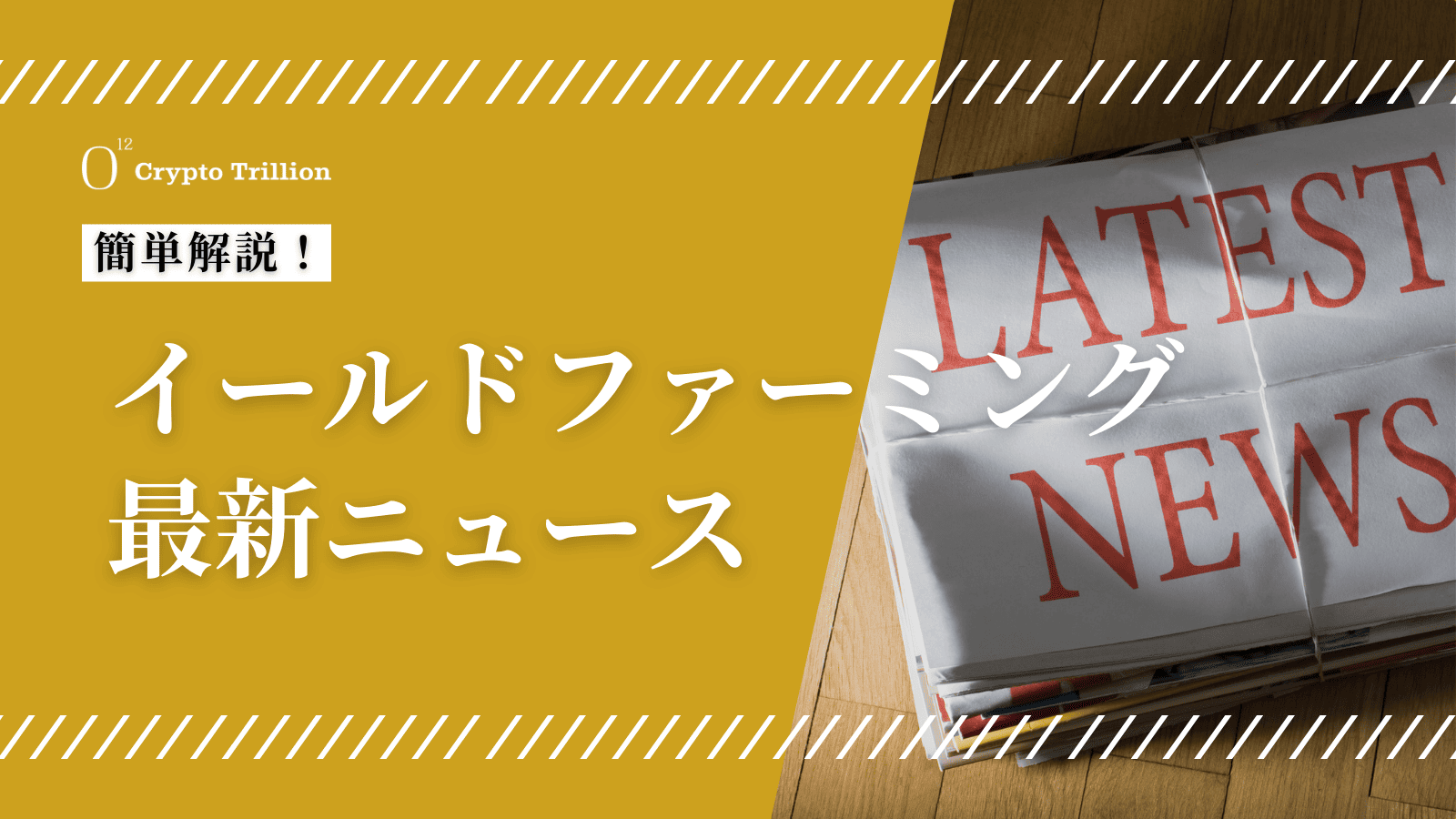
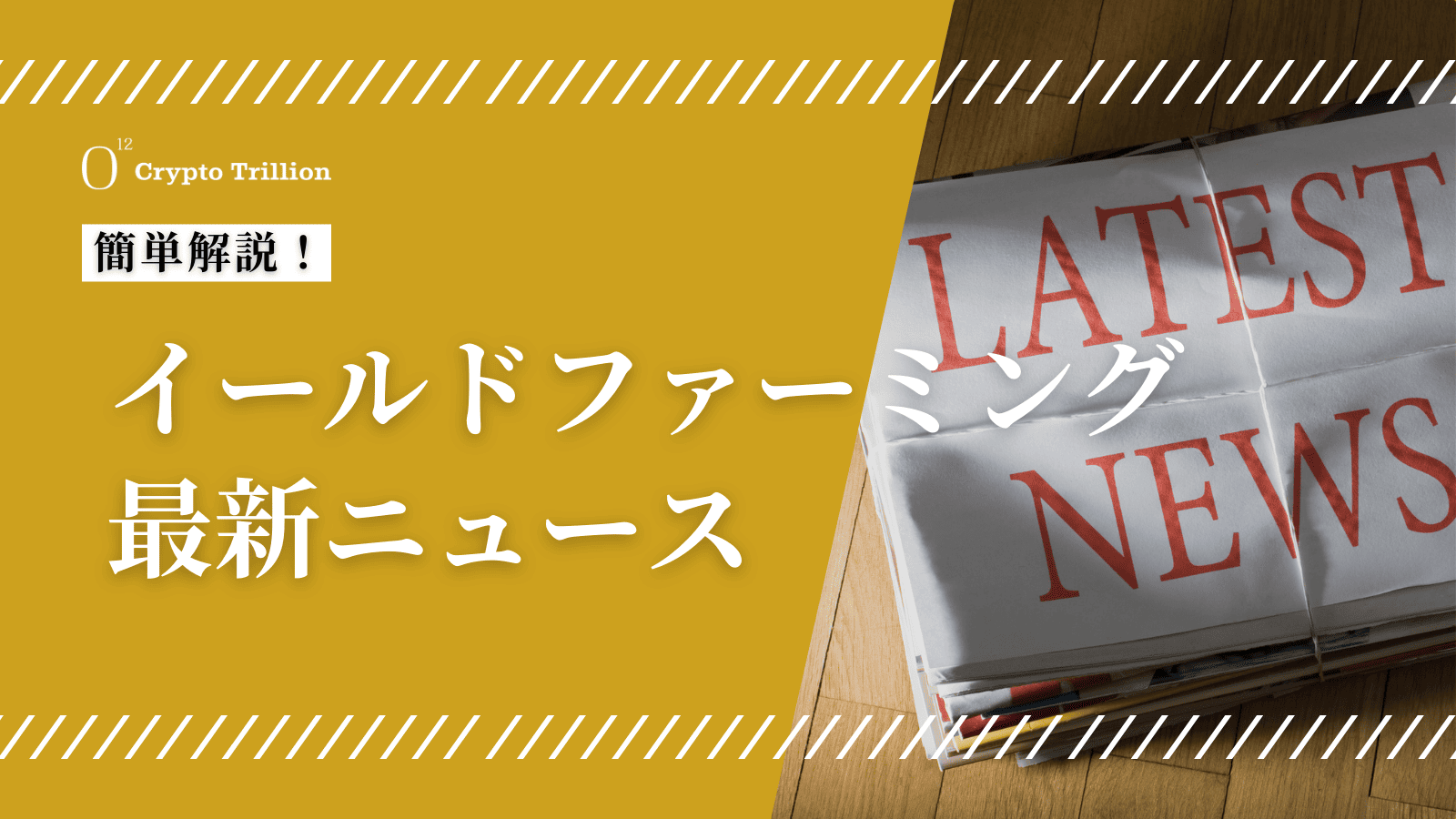
イールドファーミングの分野では、ここ1か月ほどの間に高利回り商品や新規プロトコルが次々と登場し、同時に大規模なハッキング事件や規制面での進展も報じられています。
以下では、市場動向、新規プロジェクト、規制・法整備、そしてセキュリティリスクに関する最近の話題をまとめました。
市場動向:利回りの変化と投資家の動向
暗号資産市場が活況を取り戻しつつあることを背景に、イールドファーミングの利回りが再び高水準に達しています。特に、ステーブルコイン貸付の年利が10%台をキープしているプラットフォームが複数あり、銀行の定期預金や米国債など従来の金融商品よりもはるかに高いリターンを狙える状況が続いています。
一部のプロトコルでは、レバレッジを活用した戦略が広まり、ステーブルコインの需要が急増して利回りがさらに押し上げられているケースも見受けられます。こうした動きによって、投資家が一段と仮想通貨資産へ流入するきっかけとなり、DeFi市場全体の流動性と安定性が高まっていると報じられています。
▼参考URL
新規プロジェクト・プロトコルの登場
Lazy Summer Protocol
2025年2月にローンチした「Lazy Summer Protocol」は、AIを活用した利回り最適化を掲げる新鋭プラットフォームとして注目を集めています。資産を預けると、AIが複数のDeFiプロトコルに自動で資金を再配分し、効率的にイールドファーミングを行う仕組みです。EthereumやBase、Arbitrumといった複数チェーンに対応しており、さまざまなプロトコル間での運用を一括管理できる点が魅力とされています。
公式発表によると、すでに1,800万ドル規模の資金がボールトにロックされ、ブロックチェーン・セキュリティ企業のBlock Analiticaがリスク管理を担当しているとされています。将来的には、さらに多くのチェーンやプロトコルへ対応を広げる計画もあるようです。
AaveのsGHO構想
大手DeFiプラットフォームであるAaveでは、独自ステーブルコイン「GHO」をより活用するための拡張案として、利息付与型トークン「sGHO」の導入が議論されています。sGHOを保有するとAave Savings Rate(ASR)と呼ばれる利息を自動的に獲得できるようになり、銀行の預金のような感覚でステーブルコインを運用できる仕組みです。
実現すれば、イールドファーミングと同等またはそれ以上の安定利回りを得られる可能性があるため、DeFi市場では大きな話題を呼んでいます。Aaveのガバナンスコミュニティは現在も活発に議論を続けており、具体的な導入時期などは今後のアップデートに注目が集まっています。
▼参考URL
- Decrypt: Lazy Summer Protocol Launches With an AI-Powered Yield Optimizer for DeFi
- CoinDesk: Aave DAO discussing introduction of sGHO yield-bearing token
規制・法整備の最新動向
SECが利息付きステーブルコインを承認
米国証券取引委員会(SEC)は2025年2月、Figure Markets社が提供を計画している利息付与型ステーブルコイン「YLDS」について、証券としての登録を承認しました。YLDSは米ドルに連動しながら年利3.85%を支払う設計になっており、SECが利息付きステーブルコインを公式に認めたのは初めてと報じられています。
この動きは、DeFiやイールドファーミング領域にも波及し、より多くのプロジェクトが法的に整合性の取れた形で利息付与型の金融商品を提供できる可能性を開くと見られています。一方で、ステーブルコイン関連の規制強化も進んでおり、今後は各プロジェクトがKYCやAMLなどのコンプライアンスをどの程度実装するかが焦点になりそうです。
Uniswapに対する調査終了
大手分散型取引所Uniswapの開発元であるUniswap Labsは、2024年から続いていたSECによる調査が終了し、法的措置が取られないことが決まったと2025年2月25日に発表しました。Uniswap Labsは「DeFiにとって大きな前進だ」とコメントしており、これにより今後のDeFi規制が柔軟化する兆しがあるとも言われています。
アメリカ以外でも、欧州連合(EU)や香港などでステーブルコインやDeFiの包括的規制が進んでおり、企業や投資家が安心して参入できる環境を整える動きが活発化している状況です。
▼参考URL
- Cointelegraph: SEC approves first yield-bearing stablecoin security (Figure’s YLDS)
- Cointelegraph: Uniswap announces end of SEC investigation
セキュリティ事件・ハッキング事例
直近1か月でDeFi全体におけるハッキング被害額が過去最悪水準に達しました。とりわけ、暗号資産取引所Bybitから約14億ドル相当が盗み出された事件が大きく注目を集めています。北朝鮮系ハッカー集団とみられる組織が、Bybitのマルチシグウォレット管理システムを狙ったフィッシング攻撃を仕掛け、ウォレットのバックドアを作成して資金を流出させたと報じられました。
また、複数のイールドファーミング関連プロトコルでもスマートコントラクトの脆弱性やチーム権限の悪用による資金流出が相次いでいます。大きなリスクを取る投資形態だからこそ、高い監査水準や運営体制を備えたプロジェクトを選ぶことが重要といえます。
▼参考URL
Halborn Blog: Top DeFi Hacks of February 2025
イールドファーミングを始める前の注意点
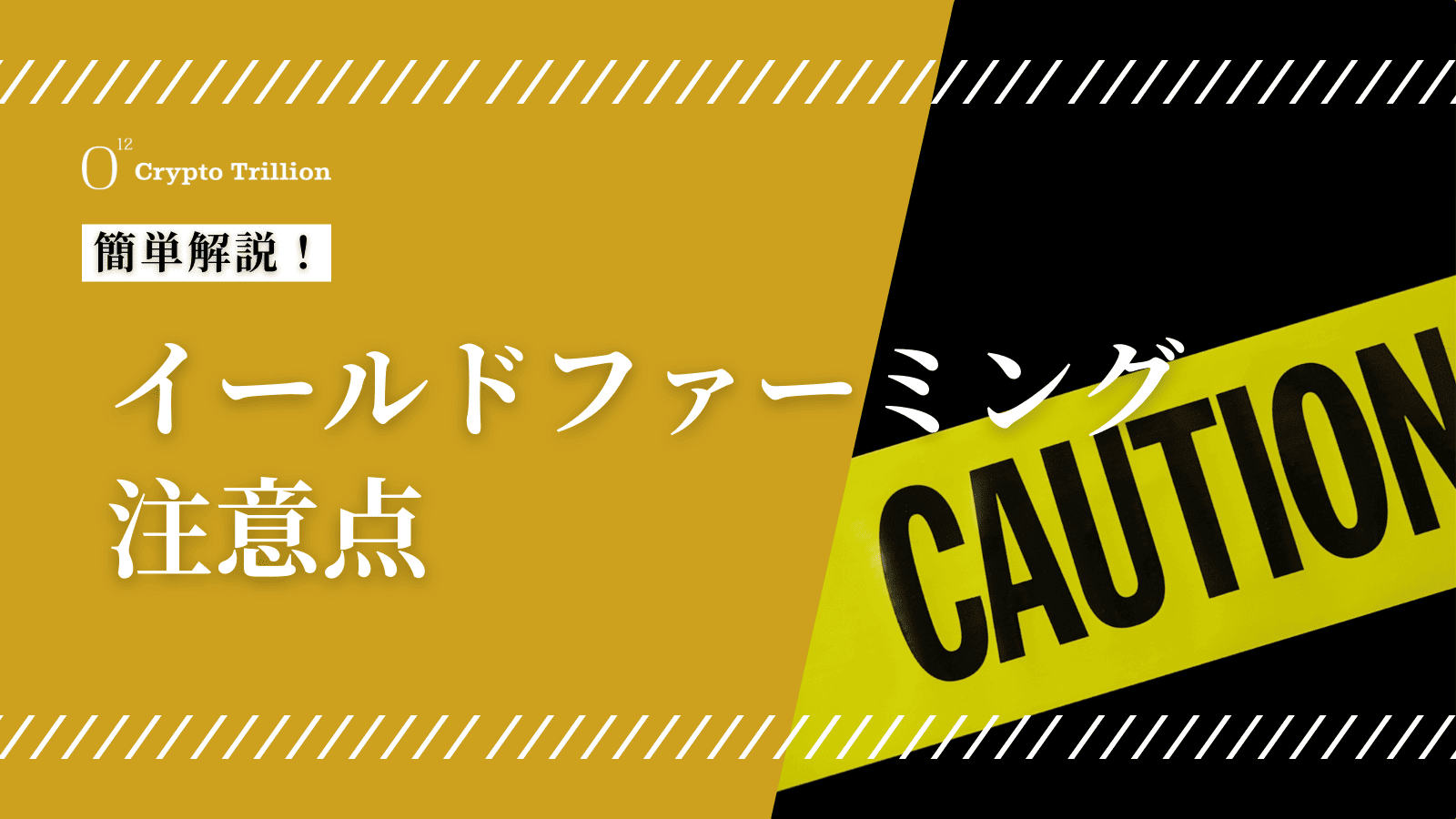
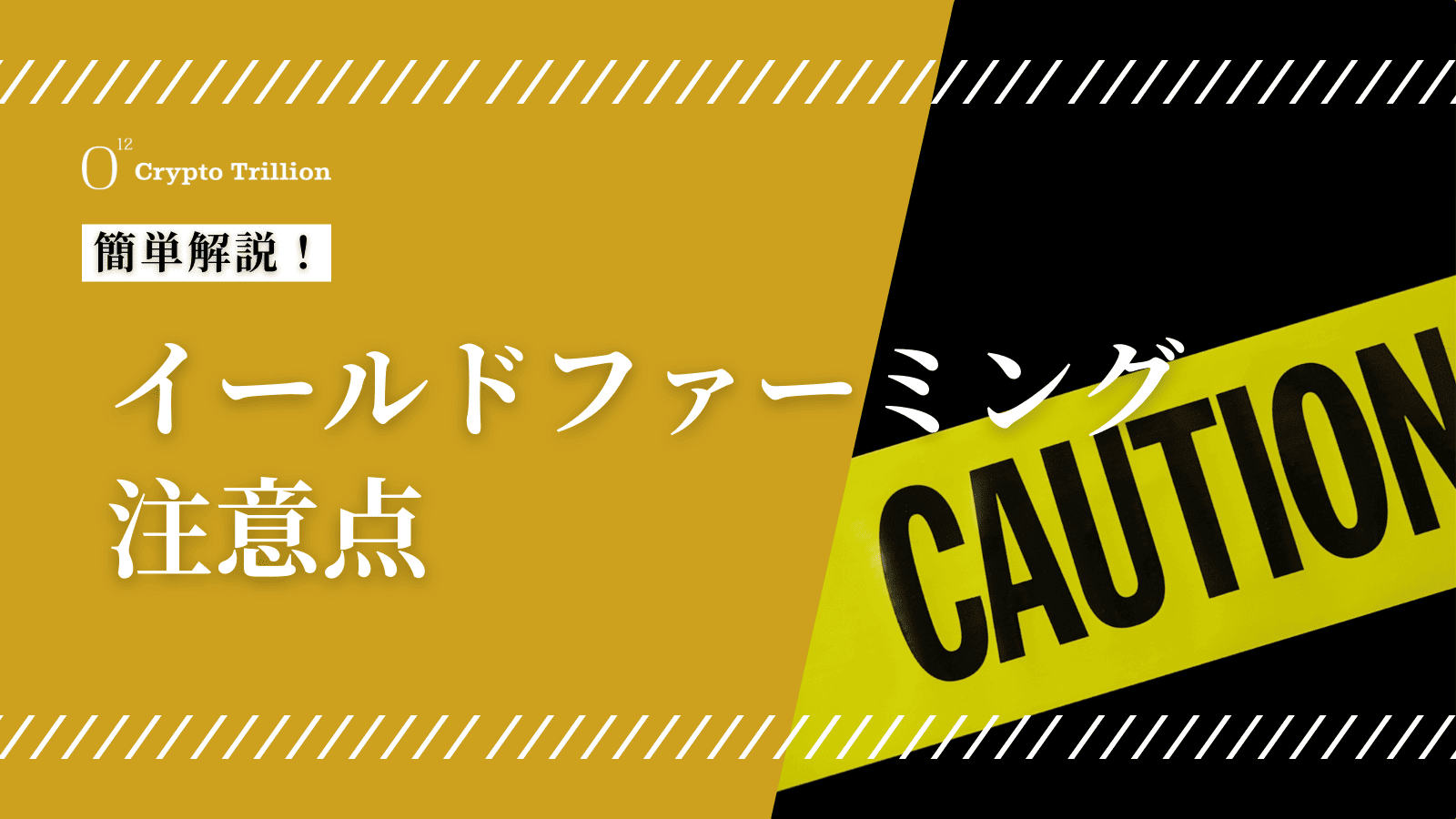
- ハイリスク・ハイリターン投資であることを理解する
- ガス代や手数料を含めた収支シミュレーションを行う
- 少額から始めて、ウォレット操作やリスク管理に慣れておくと安心
- 監査や評判を確認し、怪しいプロジェクトには近づかない
イールドファーミングを行うにあたって、まずは「最悪の場合、資金がゼロになるかもしれない」という覚悟を持っておく必要があります。
もちろん全損リスクはそこまで頻繁に起きるわけではありませんが、銀行や証券会社のような補償制度が存在しないため、事故が起きればほとんど救済は望めません。
また、仮想通貨の税制はまだ流動的な部分が多く、得られた報酬をどの時点で課税対象にするか判断が難しいケースもあります。
取引履歴や報酬を受け取ったタイミングを正確に記録し、必要に応じて税理士や専門家に相談することがおすすめです。
リスク許容度と資金管理
「仮にこの資金をすべて失っても生活に影響がない」という金額からスタートすると、安全度は高まります。
価格暴落が起きたり、プラットフォームに問題が発生したときに、慌てて生活費を取り崩す事態を避けるためです。
元本割れの可能性がある以上、余剰資金で行うのが鉄則です。投資先を一つに集中させず、複数のプールやレンディングサービスに資金を分散することで被害を抑える工夫も大切です。
プロジェクトの信用度を確認
公式サイトに監査レポートが載っているか、運営チームの実績や開発履歴、SNS上での評判などを確認してから投資する習慣を身につけましょう。
新規プロジェクトに飛びつくときは、より厳重な注意が必要です。
一時的な高い利回りに惹かれても、そのプロジェクトが1か月後や3か月後に存続できるかどうかは誰にも分かりません。周りから「これ絶対に儲かるよ」と誘われても、冷静な判断が求められます。
イールドファーミングにおけるメンテナンスとリスク回避
イールドファーミングは資産を預けるだけで報酬が得られますが、放置するとリスクも増加します。
そのため、定期的なメンテナンス(状況確認や資産の再調整)とリスク管理が重要です。
例えば、USDTとETHのペアで預け入れていた場合、ETH価格が急騰すると資産比率が変動し、インパーマネントロス(価格変動に伴う損失)が発生します。この損失を抑えるためには、価格変動の兆候を察知して、早めに資産を安定したペア(USDCとUSDTなどのステーブルコイン同士)に切り替えるといったメンテナンスが効果的です。
また、1つのプロトコルだけに大量の資金を集中すると、万が一ハッキングやトラブルが起きた際の損失も大きくなります。実際、過去には大手DeFiプロトコルのハッキングで、預けていた資産が大きく減少した事例もあります。これを避けるためには複数のプロトコルに資金を分散させ、定期的に安全性や利回りの変化をチェックすることが大事です。
こうしたリスクを回避するには、数週間に一度プロトコルの状況や利回りを見直し、必要に応じて資産の配分を調整することが推奨されます。
イールドファーミングに関するよくある質問
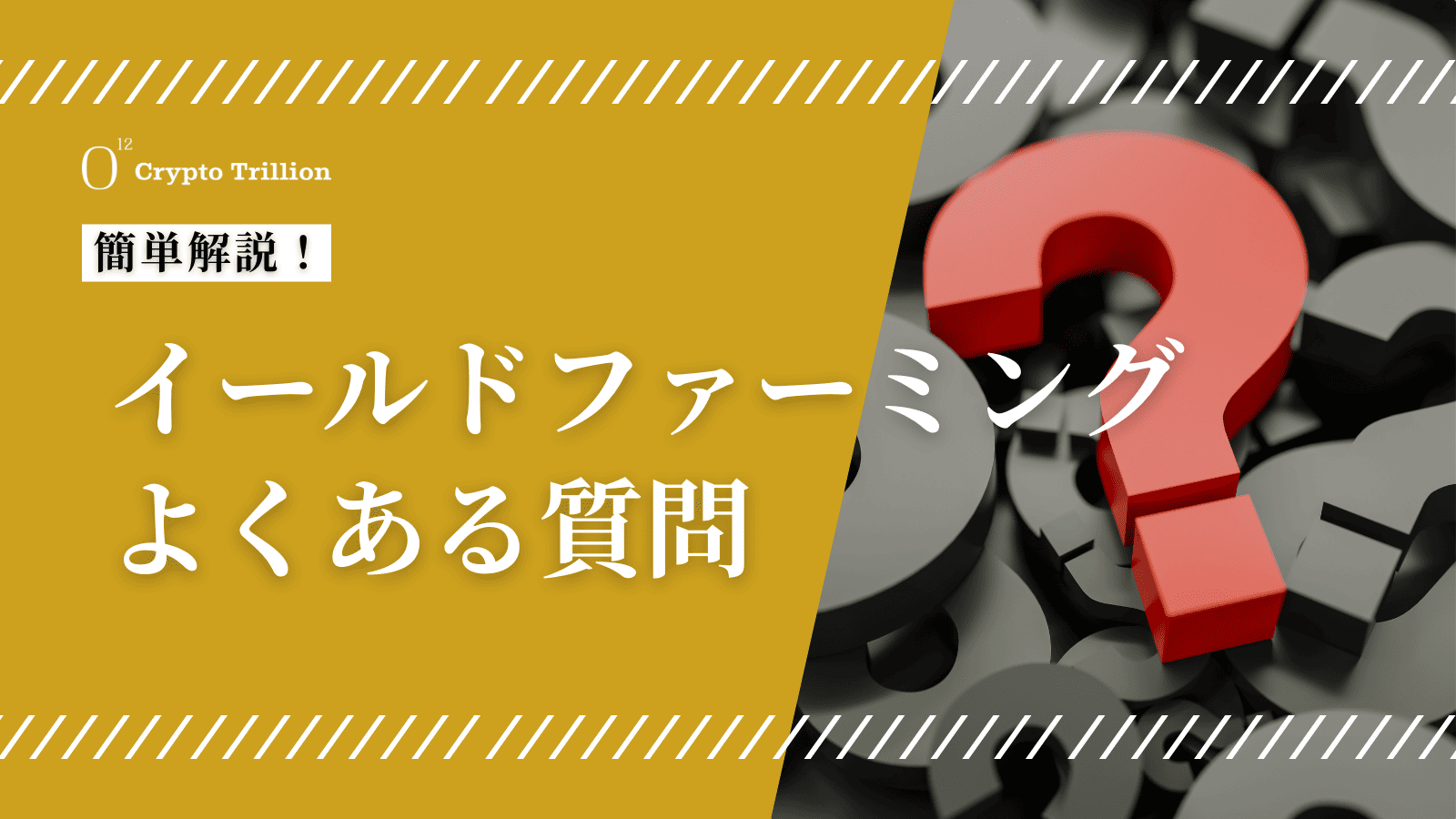
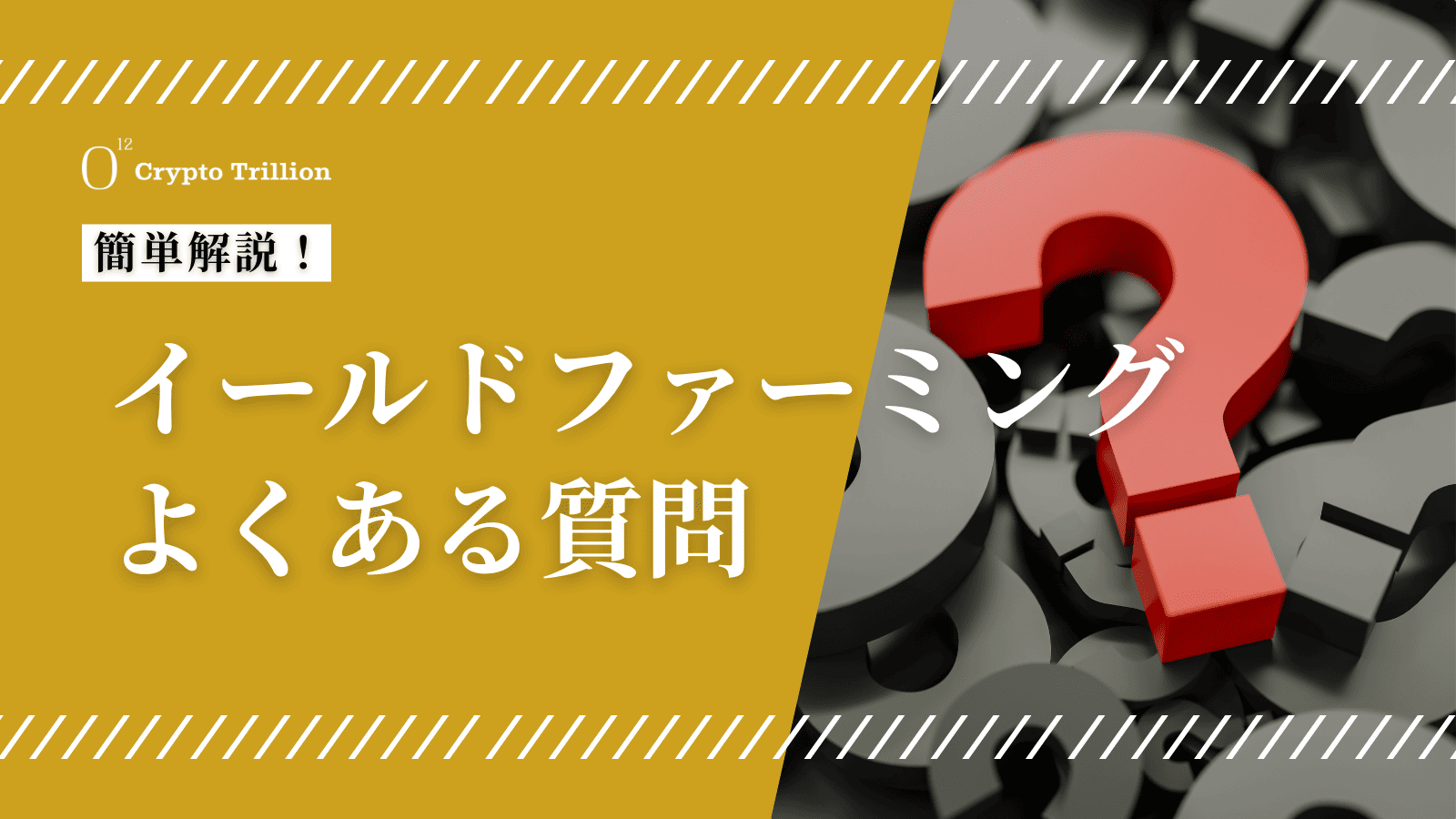
- どれくらいの資金から始めればいいのか
- ハッキングやバグ対策はどうしたらいいのか
- 税金や確定申告はどのように行うのか
どれくらいの資金から始めればいいですか?
ガス代やネットワーク手数料を考慮すると、あまりにも少額だと手数料負けするリスクがあります。ただし、最初は数千円~数万円などの範囲で操作を覚えることが大切です。いきなり大きな金額を投入すると、操作ミスやプロトコルのトラブルがあったときに取り返しがつかなくなる可能性があります。
ハッキングやバグ対策はどうすればいいですか?
ユーザー個人でできる対策は限られていますが、ウォレットのセキュリティを徹底することが一つの方法です。二要素認証やハードウェアウォレットの活用、怪しいサイトに接続しないなど、基本的な部分を怠らないようにしてください。
また、監査実績のある大手プラットフォームを選んだり、分散投資でリスクを分けたりすることも重要です。いざハッキング被害に遭うと、資金がほぼ戻ってこないのが現状なので、最初から「最悪ゼロになっても仕方ない」と割り切る心構えが必要です。
税金や確定申告はどのように行うのですか?
イールドファーミングで得た報酬は、雑所得として扱われる可能性が高いです。国内の取引所で取引する場合は取引履歴をダウンロードしやすいものの、海外のDeFiプラットフォームやウォレットは自力で履歴を記録・管理しなければなりません。
具体的な計算や申告方法は、居住地の税制によって異なります。金額が大きくなるなら、早めに税理士や専門家に相談したほうが安全です。
申告漏れや計算間違いで後々トラブルになるケースもあるので、取引ログをこまめに保存しておきましょう。
イールドファーミングとは まとめ
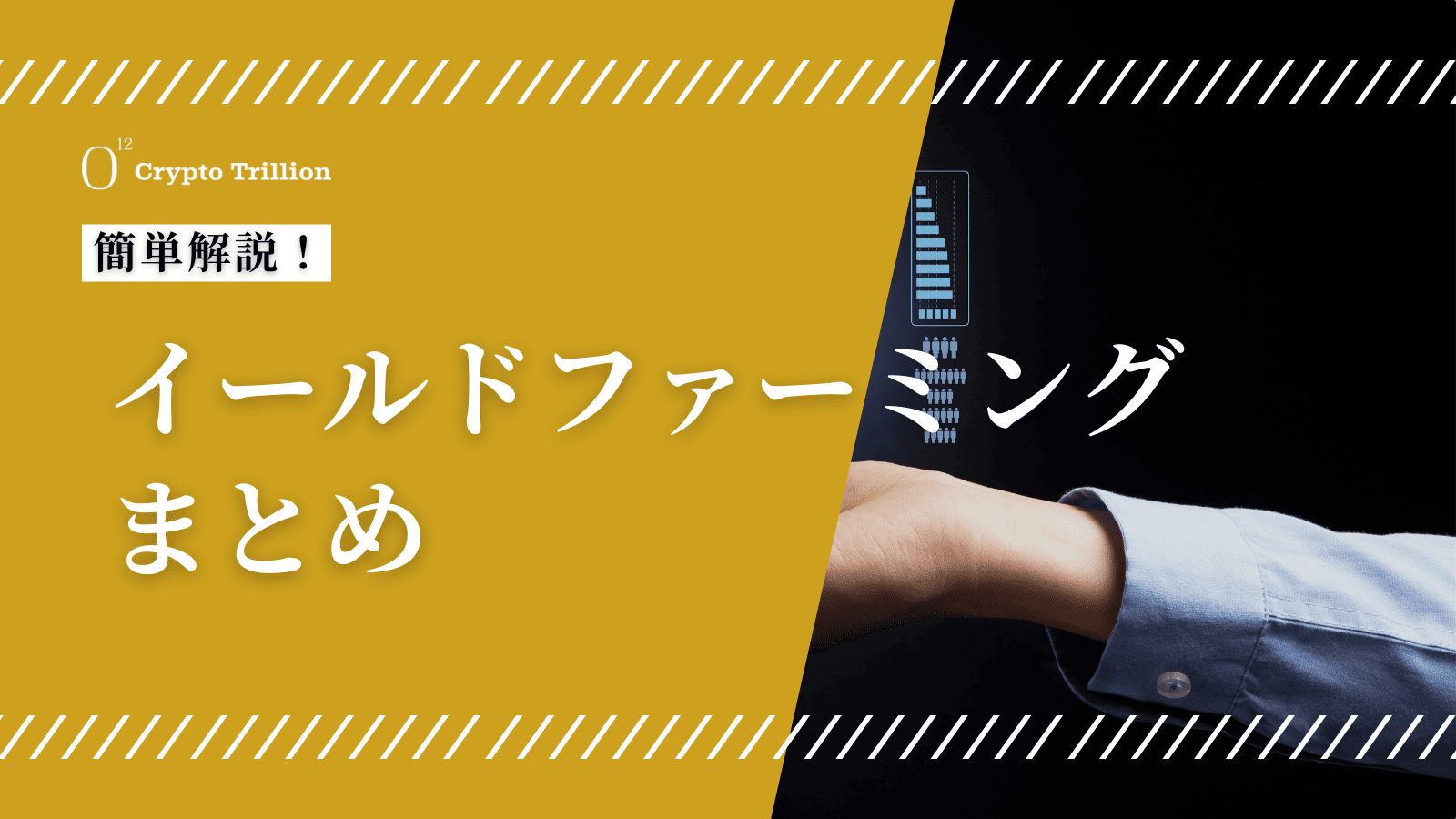
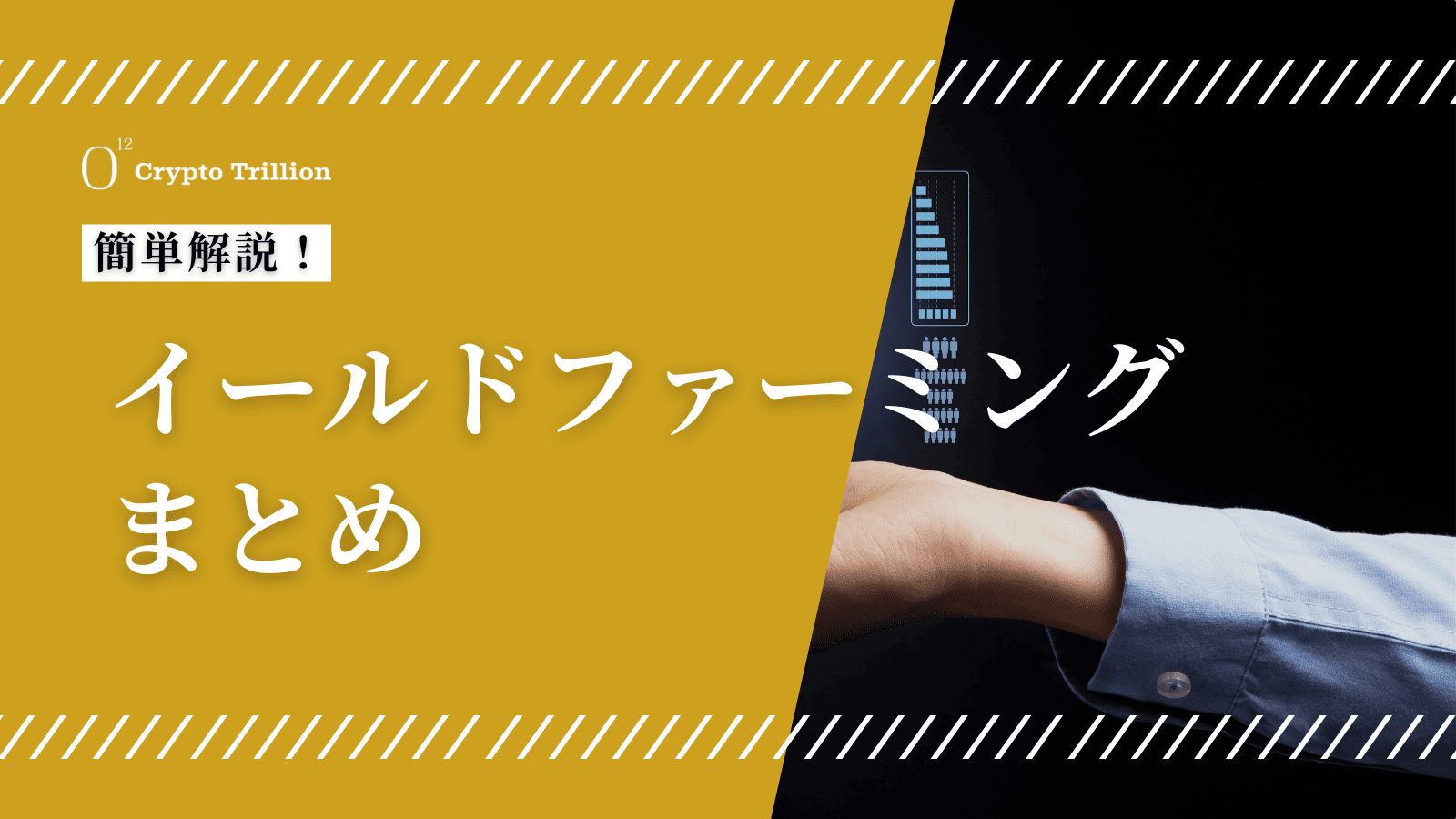
イールドファーミングは、DeFiの仕組みを活用して仮想通貨を預け入れ、高い利回りを狙える投資手法です。銀行預金や国債とは比べものにならないリターンを得られる可能性がある一方、仮想通貨の価格暴落やハッキングリスク、インパーマネントロスといった多くのリスクも存在します。
初心者であっても、少額からであれば参入自体は可能です。ただし、操作や仕組みを誤解したままだと、損失拡大や資金ロック、ハッキング被害に遭う恐れがあります。大切なのは、リスク許容度を明確にし、必要な情報を十分に収集しながら慎重に進めることです。
イールドファーミングが生む高利回りは確かに魅力的ですが、飛び込む前にまずはデメリットやリスク管理をしっかり学び、自己責任で判断する姿勢を忘れないようにしてください。必要に応じて専門家の意見も取り入れながら、着実にステップを踏んでいくことで、自分なりの安全策を備えた運用ができるようになるはずです。




