
ライトコイン(LTC)とは?特徴・将来性・今後についてニュースと一緒に解説1
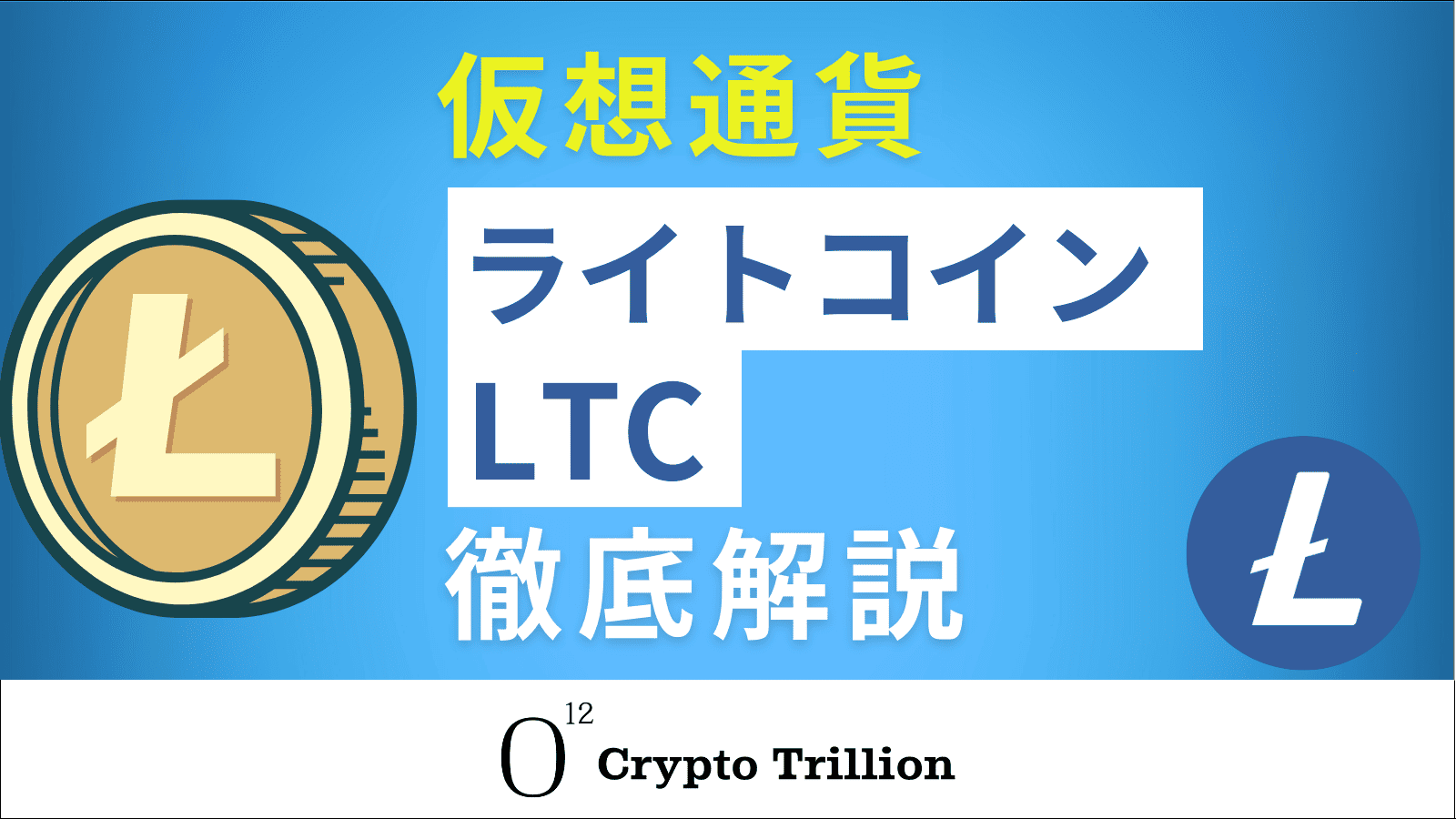
プロトレーダー Trader Zのイチ押しポイント!
- ライトコイン(LTC)は日常の支払いに使いやすい軽量通貨として発行されたアルトコイン
- ビットコインよりも取引承認が早く、発行上限も多いため実用的な運用を目指している
- ビットコインに使われていない機能を先行実装し、成功例を示すものとして開発されている
- ライトコイン(LTC)は2011年に発行され、黎明期から支えるアルトコインの一つ
- 仮想通貨のマイクロペイメントとしての可能性を見出すきっかけになる可能性がある
- ライトコインはビットコインへの機能実装に関する大きなテストベッドになっている
- 技術開発とそのロードマップを堅実にこなしているため、ビットコインの成長の一因にもなる可能性がある
- ライトコインの将来性や今後は、いかに支払いに関する機能を実装できるかに左右されると考えられる
- ETF承認の可否や大手金融機関の主要アルトコインへの扱いなど、資金流入の選択肢は複数ある
- 今後はマイクロペイメントの実用化に向けて支払いに関する開発の進み具合が指標になる
- ライトコイン/LTCは、手数料無料のGMOコインで購入するのがおすすめ!
 Trader Z
Trader Zライトコイン(LTC)はビットコインの可能性を拡大するためにある通貨だと私は考えます。



ビットコインの弱点と言われているのはスケーラビリティ、マイクロペイメントなどど言われており、実際に送金詰まりや手数料の高さも否めません。
ただ、実用化をずっと目指しているのであれば、開発が遅いと思われている部分もあり雲行きが怪しいと考える人もいます。
今後は本格開発や金融機関からの資金流入について見ることが値動きを左右するのではと個人的に考えます。
\日本円の入出金・仮想通貨の送金手数料無料!/


Trader Z
ディーリングアドバイザー
世界第3位の仮想通貨取引所であるMEXCのトレーダーランキングにおいて、常に上位にランキングされる世界有数のトレーダー。
2024年10月には1,229,864,919.71USDT(日本円に換算して 1920 億円)の取引を行い、第1位となる。2024年12月にGFA Capital社が行う暗号資産ディーリング業務のアドバイザーに就任。


監修 Trader Z
ディーリングアドバイザー
世界第3位の仮想通貨取引所であるMEXCのトレーダーランキングにおいて、常に上位にランキングされる世界有数のトレーダー。
2024年10月には1,229,864,919.71USDT(日本円に換算して 1920 億円)の取引を行い、第1位となる。2024年12月にGFA Capital社が行う暗号資産ディーリング業務のアドバイザーに就任。
ライトコイン(LTC)とは?
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 正式名称 | Litecoin(ライトコイン) |
| ティッカーシンボル | LTC |
| ローンチ時期 | 2011年(公開: 2011年10月頃) |
| 対応チェーン | Litecoin独自のブロックチェーン |
| 通貨の種類 | 決済用暗号資産(アルトコイン) |
| 公式サイト | https://litecoin.org/ |
| 公式SNS | Twitter: @Litecoin |
ライトコインは、2011年に元Googleエンジニアのチャーリー・リー氏によって公開された暗号資産です。
ビットコインを「デジタルゴールド」に例えるなら、ライトコインは「デジタルシルバー」に相当すると言われており、比較的日常の支払いに使いやすい軽量通貨として設計されています。
具体的には、ビットコインよりも取引の承認が早く、発行上限も多い点が大きな特徴です。
ライトコインは「ビットコインでは使われていない機能を先行実装し、成功例を示す役割を果たしてきた通貨」としても有名です。
最初の頃から主要取引所で取り扱われ、時価総額でも上位に名を連ねています。
日本国内ではビットコインの次に知名度があるアルトコインの一つとして認識されてきました。
2024年以降はアメリカでのETF化に向けた動きなど、さらに注目を集めるニュースが続いています。
ライトコイン(LTC)の特徴と仕組み
- 発行上限は8,400万枚でブロック生成は約2分30秒
- Scryptというアルゴリズムを採用し、マイニング面でビットコインと異なる
- 送金目的の決済通貨としての利用を想定している
発行枚数・ブロック生成の速さ
ライトコインは発行上限が8,400万枚であり、これはビットコインの4倍に当たります。
ビットコインが2,100万枚という限られた発行数を持つ一方、ライトコインは上限を増やすことでより多くの人が使いやすい環境を整えています。
ブロックチェーンの取引記録を生成する時間はおよそ2分30秒ほどです。
ビットコインは10分程度かかる設計なので、その4倍ほど速い計算になります。
送金に必要な承認回数にもよりますが、ビットコインよりも短時間で決済を完了しやすい点が長所として挙げられます。
アルゴリズム(Scrypt)の特徴
ライトコインが採用しているScryptは、ビットコインが用いるSHA-256とは異なるハッシュアルゴリズムです。
開発初期の狙いとしては、専用ハードウェア(ASIC)による寡占を防ぎ、一般ユーザーがCPUやGPUでもマイニングに参加できるようにする目的がありました。
しかし現在はScrypt対応のASICも登場しており、一部では高性能な専用機器を使ったマイニングが主流となっています。
それでもライトコインのコンセンサスアルゴリズムはビットコインと同じProof of Work(PoW)に分類されており、多数のマイナーがネットワークを支えています。
ビットコインほどのマイニング競争ではないとはいえ、それなりのハッシュパワーが集まっていることが安全性を維持するポイントになっています。
ビットコインとの主な共通点・相違点
ライトコインのブロックチェーンはビットコインと同様にオープンソースで公開され、公開当初はビットコインのコードをフォーク(分岐)して誕生した経緯があります。
共通点としては、暗号学的手法を用いるPoW型のネットワークであることや、半減期(約4年ごとにマイニング報酬が半減する仕組み)が存在することが挙げられます。
相違点としては、ブロック生成時間が短いことや発行上限が多いこと、使っているハッシュアルゴリズムが違うことなどがあります。
ビットコインの大規模な送金手数料が高騰しがちな局面では、ライトコインのような速くて安い通貨が代替手段として注目されるケースも少なくありません。
ライトコイン(LTC)が有名になった理由
- 2011年誕生という初期から続く歴史が信頼感を生んだ
- ビットコインの機能を先行実装してきた事例が多い
- 開発を支えるコミュニティの存在が大きい
歴史的背景:主要アルトコインの先駆け
ライトコインは2011年という早期に登場したアルトコインで、当時は暗号資産の種類自体が非常に少なかったこともあり、いち早く世界的な注目を集めました。
誕生直後から複数の取引所で取り扱われ、取引量や時価総額も安定して上位に位置していたことが影響しています。
「ビットコインの次に古い主要アルトコイン」というポジションにより、黎明期から持続的に利用されてきた実績が積み上がり、相対的な安心感を与えてきました。
暗号資産市場では新しい銘柄が次々と誕生し、消えていくものも少なくないなか、10年以上生き残っている通貨はごくわずかです。
その一つとしてライトコインが挙げられる点は大きいかもしれません。
SegWit・Lightning Network導入の先行事例
ライトコインは開発者コミュニティが積極的に新技術を取り入れることで知られています。
ビットコインで大きな議論となったSegWit(セグウィット)導入の際も、ライトコインが先行して実装し、実運用でのメリットを証明してみせました。
ブロックサイズ問題や手数料削減など、ビットコインが抱えていた課題を解決する可能性があるアップデートを先に導入したことで、「ライトコインはビットコインのテストベッドとして機能している」という評価を得たのです。
ライトニングネットワークも同様で、早期にマイクロペイメントのテストを行い、将来的な拡張性を示す場として注目されました。
ビットコインでは慎重に行われるアップデートをいち早く実装して結果を確認できる点は、コミュニティの積極性や柔軟性を示しています。
コミュニティと開発体制の安定
ライトコインにはLitecoin Foundation(ライトコイン財団)という非営利組織が存在し、開発や普及活動をリードしています。
チャーリー・リー氏をはじめとする主要メンバーが定期的に情報発信を行い、新機能のテストやパートナーシップの検討などを進めているのが特徴です。
リー氏が個人的にライトコインをすべて手放したことが過去に話題になりましたが、財団や開発者コミュニティはその後も継続してアップデートを行い、実際にライトコインネットワークは止まることなく稼働し続けています。
開発者の個人的思惑に左右されず、分散型のコミュニティによって支えられていることは、長期的に信頼を寄せられる理由の一つといえます。
ライトコイン(LTC)に関するニュース
- ライトコインETF承認の可能性が高まっている
- 大手金融機関による採用や連携が拡大
- 価格や取引量の推移にも注目が集まっている
ライトコイン(LTC)ETF承認への期待
2025年現在、米国ではビットコインやイーサリアムに続き、ライトコインの現物ETFを複数の資産運用会社が申請している状況です。
米国証券取引委員会(SEC)の審査手続きに入っており、早ければ年内にも可否が判断されるという見通しが語られています。
ビットコインがETF承認で大きく注目された経緯があるように、ライトコインも正式にETFが承認されれば機関投資家などの新規参入が見込まれるかもしれません。
こうした期待感によって、ライトコイン関連の報道や投資家の関心は高まっているようです。
機関投資家や大手金融機関との連携
大手金融機関であるフィデリティやブラックロックなどが、暗号資産向けの投資サービスを拡充しており、その対象にライトコインが含まれています。
ビットコインやイーサリアムほど規模は大きくないものの、複数の金融商品でライトコインが取り扱われる計画があると報じられています。
これまで主流金融機関はビットコインを最優先に扱ってきましたが、次の候補としてライトコインやリップルなどメジャーなアルトコインに対象を広げる傾向が見られます。
こうした流れは暗号資産の一部が投機対象にとどまらず、資産形成の選択肢として認められる兆しとも言えるでしょう。
市場価格・トレンドの動向
ライトコインは2024年末頃から取引量が増加し、ETF承認期待などの好材料が重なって一時的に価格が上昇した局面がありました。
その後の全体相場の下落局面も受けて、2025年4月あたりでは一服状態にあるようですが、オンチェーンデータでは活発な取引が継続しているとの分析も見られます。
市場全体の動向に左右される部分は大きいものの、ライトコイン単独でも今後の規制状況や技術アップデートが直接的に価格に影響する可能性があります。
とくにETF関連のニュースは一気に市場センチメントを変えることがあるため、暗号資産全般のトレンドとあわせて注目が集まるところです。
ライトコイン(LTC)に関する過去の事件
- チャーリー・リー氏の保有LTC売却はコミュニティで物議を醸した
- LitePayプロジェクト中止やWalmart提携フェイクニュースなど話題があった
- プライバシー強化アップデートが規制面で問題視された例がある
創設者チャーリー・リーの全売却騒動
2017年末の仮想通貨バブル期、ライトコイン価格が大きく上昇したタイミングで、創設者のチャーリー・リー氏が保有していたすべてのライトコインを売却したと公表しました。
リー氏は「自身の発言が価格に影響を与え、利益相反の懸念があるため」と説明していましたが、最盛期の高値で売り切ったと見られることから一部で批判も出ました。
本人はあくまで「プロジェクトへのコミットは継続する」としていましたが、コミュニティの一部では「創設者のモチベーションが下がったのではないか」と疑う声もありました。
結果的にはその後もアップデートは続き、リー氏も開発や啓発活動に携わっています。
LitePay頓挫とWalmartフェイクニュース事件
2018年前後にライトコイン向けの決済サービス「LitePay」が大きな期待を集めたものの、経営や資金面の問題からプロジェクトが突然中止になったことがありました。
ライトコイン財団も支援しようとしていましたが、最終的には説明不足を理由に撤退し、投資家やコミュニティに謝罪する事態となっています。
さらに2021年には、米小売大手ウォルマートがライトコイン決済に対応するという偽のプレスリリースが出回り、多くのメディアが報じて価格が急騰しました。
しかし数十分後にウォルマート社が否定し、誤報であったことが明るみに出ています。
発表当時ライトコイン財団の公式アカウントがこの報道をリツイートしてしまった経緯も重なり、暗号資産市場の情報の不確かさを象徴する出来事として記憶されています。
プライバシー機能(MWEB)導入と規制の問題
ライトコインは2022年にMimbleWimble Extension Blocks(MWEB)と呼ばれるアップグレードを実行し、取引の機密性を高めるオプションを導入しました。
取引額やアドレス情報を隠せる設計はユーザーにとって利便性が高まる一方で、マネーロンダリングなどの違法行為に利用される可能性があるとして、韓国の主要取引所が一斉にライトコインを上場廃止する動きに出ました。
プライバシー機能を備えた通貨は各国の規制当局から厳しく監視される傾向があります。
ライトコインの場合はオプション形式だったものの、匿名送金の可能性があること自体が問題視されたようです。
これによって一部地域では流動性が低下しましたが、海外の大規模取引所では上場を続けているため、グローバルな影響は限定的なまま推移しています。
ライトコイン(LTC)の将来性・今後の展望
- 技術的な進化は継続中で、MimbleWimble以外のアップデートも期待される
- 決済通貨としての実利用が広がっている
- 専門家の価格予想は穏健ながらETF承認など好材料もある
技術アップデートと開発ロードマップ
ライトコインはビットコインの技術的アップデートを取り入れる形で進化してきました。
SegWitやライトニングネットワークの実装に加え、最近ではTaprootの要素を組み込む検討も行われています。
開発者コミュニティが活発に活動している間は、今後も新機能の実験や採用が続くかもしれません。
MimbleWimbleのような独自アップデートも含め、支払い通貨として使いやすくするための取り組みが継続されると考えられています。
アプリケーション層での利用事例が拡大すれば、ライトコインの存在感がさらに高まることもあるでしょう。
決済通貨としてのポテンシャル
ライトコインはブロック生成が速く手数料が安い特性から、実際の決済シーンで使いやすいと言われてきました
BitPayなどの決済サービス大手がライトコインをサポートし、ビットコインよりも使用回数が多い時期があったという報告もあります。店舗決済においては、支払い手数料や承認待ち時間の短さが非常に重要です。
ビットコインがスケーラビリティを確保しきれないタイミングではライトコインが代替手段として機能する可能性があります。
特に、カジュアルに暗号資産決済を導入している海外の中小事業者やオンラインショップなどでは、ライトコインを受け付ける例が増えてきました。
投資・価格予想と専門家の見解
投資対象としてのライトコインは、ビットコインやイーサリアムほどの大幅な価格上昇こそ期待しにくいと見る向きもありますが、長年市場に定着してきたブランド力と流動性の面では今後も一定の需要が続くと考える専門家が多いです。
ETFが承認されれば新たな資金流入が生まれ、価格上昇につながる可能性はありますが、あくまでも市場全体や規制の動向に影響される要素が大きいかもしれません。
ライトコインを購入したいと考える場合、ボラティリティが高い点を踏まえ、中長期的な視点で運用するかどうか検討すると良いでしょう。
コミュニティの規模や技術開発の進捗、決済サービスとの連携状況なども総合的に判断することが望ましいです。
ライトコイン(LTC)とは まとめ
ライトコインは10年以上の歴史を持ち、ビットコインを補完する決済通貨として一定の地位を築いてきました。
過去には創設者の保有売却やフェイクニュース騒動など話題に事欠かない面もありましたが、そのたびにコミュニティが立て直し、現在も開発や普及活動が活発に続けられています。
技術的にはSegWitやライトニングネットワークを先行導入してきた実績があり、新しい提案を柔軟に取り入れる姿勢も評価されています。
2025年4月時点では、ライトコインETFの承認や大手金融機関との連携が注目を集めており、市場からの評価が再び高まりつつあるといえます。
投資対象として見る場合でも、決済手段として実際に使う場合でも、ビットコインだけでなくライトコインにも興味を広げてみる価値はあるかもしれません。
とはいえ、価格変動リスクや規制の問題など、暗号資産固有のデメリットも存在するため、常に十分な情報収集とリスク管理を意識することが大切です。

