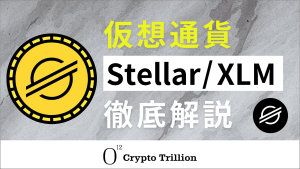ステラルーメン/XLMとは?今後・将来性について専門家に聞いた結果を紹介!
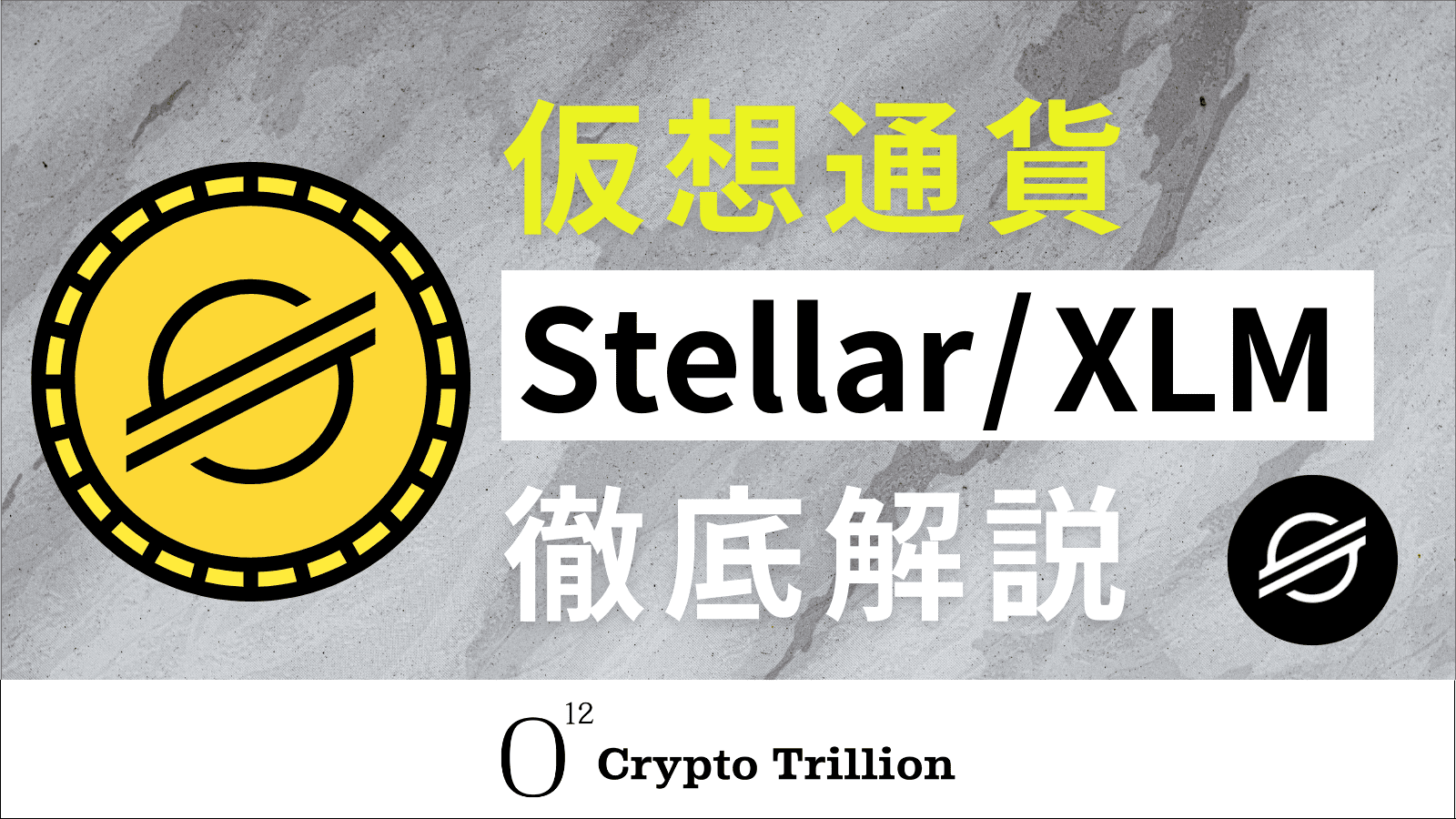
プロトレーダー Trader Zのイチ押しポイント!
- ステラルーメン/XLMとは国際送金や金融包摂を目的とした仮想通貨プロジェクト
- XRPと少し似ている部分があり、競合としてよく名が上がっている
- 高速送金や約0.0003円ほどの低手数料が魅力のブロックチェーン
- XRPとの違いは中央集権型の承認システムではなく、分散型のシステムを使用していること
- 大手企業や金融機関との連携が目立ち、実用的なシステム開発にも踏み込んでいる
- 国連開発計画(UNDP)との提携や、中央銀行とのステーブルコイン開発が検討されている
- IBMやMoneyGram、MasterCardなど大手との協業が目立つプロジェクト
- ステラルーメン/XLMの今後はDeFi・DEX分野でどれくらいシェアを伸ばせるかだと考えられる
- Sorobanというスマートコントラクト機能の導入を本格化してきている
- 決済手段としての実用化が進むにつれ、DeFi・DEX分野での魅力が出てくる
 Trader Z
Trader Zスマートコントラクト機能の実装によって今後のDeFi市場にどのくらい食い込めるかが肝心になってきますね!
決済や送金を目的としたブロックチェーンでは、ステーブルコインがよく使われるため、スマートコントラクト機能実装は個人投資家にとって嬉しい報告となるのではないでしょうか?



ステラルーメン/XLMは国内取引所にも上場しています。
もしXLMの将来性を信じて購入する場合は、長期保有に向けサービスが豊富なコインチェックでの購入がおすすめです。
\初めての仮想通貨取引でも簡単!/


Trader Z
ディーリングアドバイザー
世界第3位の仮想通貨取引所であるMEXCのトレーダーランキングにおいて、常に上位にランキングされる世界有数のトレーダー。
2024年10月には1,229,864,919.71USDT(日本円に換算して 1920 億円)の取引を行い、第1位となる。2024年12月にGFA Capital社が行う暗号資産ディーリング業務のアドバイザーに就任。


監修 Trader Z
ディーリングアドバイザー
世界第3位の仮想通貨取引所であるMEXCのトレーダーランキングにおいて、常に上位にランキングされる世界有数のトレーダー。
2024年10月には1,229,864,919.71USDT(日本円に換算して 1920 億円)の取引を行い、第1位となる。2024年12月にGFA Capital社が行う暗号資産ディーリング業務のアドバイザーに就任。
ステラルーメン/XLMとは何か?
- 2014年にリップル共同創業者のジェド・マケーレブによって設立
- 非営利組織Stellar Development Foundation(SDF)の運営
- 送金プラットフォームとしての役割を重視し、金融包摂に注力
送金・金融包摂に特化した仮想通貨
ステラルーメンは「国際送金」や「金融包摂」といった分野に焦点を当てた仮想通貨・ブロックチェーンプロジェクトです。
銀行口座を持たない人々でも気軽にアクセスできる環境を提供し、新興国や個人同士の小額送金など、既存の金融インフラがカバーしきれていない領域を補完することを目指しています。
世界には銀行サービスを利用できない人が多数存在するとされ、それが貧困の要因になっているという見方もあります。
そのため、安価かつ迅速に価値をやり取りできるステラルーメンの仕組みは、こうした課題の解消に活用できる可能性があります。
また、ステラルーメンはしばしばリップル(XRP)と比較されます。
どちらも国際送金に強みをもつことで有名ですが、リップル社は法人向けのソリューション提供を重視しているのに対し、ステラルーメンは個人や地域コミュニティにも焦点を当てています。
運営形態も営利企業か非営利財団かという点で異なるため、同じ送金特化型とはいえ使われ方や提携先のタイプには違いがあります。
誕生の背景と開発者
ステラルーメンは2014年にスタートしました。
創設者はジェド・マケーレブという人物で、過去にリップル(XRP)の共同創業者としても活躍していたことで知られています。
マケーレブはビットコイン黎明期から仮想通貨と深く関わってきた経歴を持ち、かつては世界初期のビットコイン取引所Mt. Goxを手掛けていたことでも話題を集めました。
その後、マケーレブはリップル社を離れ、新たに非営利組織Stellar Development Foundation(SDF)を設立します。
SDFは企業形態であるリップル社とは異なり、「誰もが使えるグローバルな送金・金融インフラを構築する」という社会的使命を掲げて活動しているのが特徴です。
寄付や助成金、企業からの協賛などで資金を調達し、ネットワークの開発や啓蒙活動を行ってきました。
営利を主目的としない財団運営であるため、利益を配当する株主が存在せず、その分技術開発や普及施策に注力できる体制といわれています。
ステラルーメン/XLMの特徴・技術的仕組み
- 独自コンセンサス「Stellarコンセンサスプロトコル(SCP)」
- ネイティブ通貨ルーメン(XLM)の用途
- 低手数料・高スケーラビリティで多様な決済ニーズに対応
ここでは、ステラルーメンがどのような技術的特徴を持ち、なぜ高速かつ安価な送金を実現できるのかを紹介します。
Stellarコンセンサスプロトコル(SCP)と高速決済
ステラルーメンが高い処理性能を発揮できる理由の一つは、Stellarコンセンサスプロトコル(SCP)と呼ばれる合意形成方式を採用していることです。
これはフェデレーテッド・ビザンチン合意(FBA)モデルに基づく仕組みで、各ノードが互いを信頼関係に基づいて選ぶことで全体として合意が成立するようになっています。
ビットコインやイーサリアムのプルーフ・オブ・ワーク(PoW)のように多大な計算資源を必要とせず、数秒単位で取引が確定するため、送金の待ち時間や手数料を抑えることができます。
また、この高速決済は金融機関や個人が利用する際にもメリットが大きいと考えられます。
トランザクションの確定速度が速いほど、送金相手が遠い国や地域であっても素早く資金が着金することになるからです。こうした実用性の高さがステラルーメンの魅力の一つになっています。
ネイティブトークン「ルーメン(XLM)」の用途
ステラルーメンネットワーク上で使われるネイティブ通貨は「ルーメン(XLM)」と呼ばれています。
XLMは、ステラルーメンネットワークを使用する際の、手数料支払いにXLMが用いられます。
ステラルーメンは手数料が非常に低廉で、送金一回あたり0.00001XLM(0.0003円)程度に設定されていることが多いです。
これはネットワークのスパム攻撃を防止するための仕組みでもあり、トランザクションを承認するたびにごくわずかなXLMが消費される形になっています。
異なる通貨同士の交換を行う際のブリッジ(仲介)としてXLMが利用されることもあります。
例えば法定通貨Aから法定通貨Bへ直接交換するのではなく、いったんXLMに替えてから別の通貨へ変えることで、取引の柔軟性を高めるわけです。
手数料の安さと高いスケーラビリティ
ステラルーメンは手数料が非常に安く、なおかつ大量の取引に対応できるスケーラビリティを備えています。
これはSCPの仕組みや全体的な設計方針によって実現されているものです。
ビットコインやイーサリアムの場合、ネットワークが混雑すると手数料が高騰したり、決済に時間がかかったりすることがあります。
一方でステラルーメンは少ない手数料で迅速に取引を処理できるため、小額送金や頻繁な決済が必要な場面に適しているといわれています。
またスケーラビリティの高さは、銀行や大手企業が導入するうえでも重要な要素です。
将来的に利用者が増えた場合でも、一定のコストや速度を維持できる見込みがあるため、多くの企業や団体がステラルーメンの活用を検討していると報じられています。
なぜステラルーメン/XLMはここまで有名になったのか
- IBMやMoneyGramなどの大手企業との協業
- 金融機関のステーブルコイン発行事例が後押し
- 金融包摂や社会貢献を重視する姿勢でコミュニティが拡大
大手企業・金融機関との提携事例
ステラルーメンが広く知られるようになった大きなきっかけとして、IBMの「World Wire」プロジェクトで採用されたことが挙げられます。
IBMはグローバルなテクノロジー企業であり、多数の銀行や金融機関と連携していますが、国際送金の効率化を目的にステラルーメンの技術を活用しました。
その結果、金融機関同士が法定通貨やステーブルコインを素早くやり取りできる枠組みが提供され、業界から強い関心を集めることになります。
続いてMoneyGramなど、送金サービス大手との協業も注目度を高める要因になりました。
MoneyGramは多くの国や地域に拠点を持ち、現金送金ネットワークを展開している企業です。
同社がステラルーメンを通じて暗号資産との交換サービスを提供するようになったことは、ブロックチェーン技術がより一般的な決済の現場に入り込むきっかけになったともいわれています。
さらに、フランスの大手金融グループであるソシエテ・ジェネラルの子会社SG-Forgeがステラルーメンを活用してユーロ連動ステーブルコインを発行したことも大きな話題の一つです。
こうした事例は「ステラルーメンは銀行や規制当局からの信頼を獲得しつつある」という印象を市場に与え、XLMの地位を高めるきっかけになったと考えられます。
社会的インパクトとコミュニティの支援
ステラルーメンは創設当初から金融包摂(金融インクルージョン)の推進を掲げており、新興国や銀行口座を持たない人々向けにエアドロップや啓蒙活動を積極的に行ってきました。
このような社会貢献性の強い取り組みは、コミュニティからの強い支持を得ることにつながっています。
企業や投資家にとっても、公益性が高いプロジェクトに参加することはブランドイメージの向上につながるため、ステラルーメンに興味を示す動きが続いています。
また、非営利財団としての運営方針も、他の営利企業が提供する暗号資産プラットフォームとは一線を画すポイントです。
収益目的だけでなく、長期的な普及や技術革新を重視する姿勢があると受け取られることで、規制当局や国際機関からも協力を得やすい環境になっているようです。
ステラルーメン/XLMに関するニュース
- 「Soroban」アップデートが進み、スマートコントラクト領域へ本格参入
- UNDPやMastercardなど国際機関・大手企業と新規協業
- 各国政府・銀行によるCBDCやステーブルコイン利用に期待感
主なアップデート「Soroban」の進捗
ステラルーメンは2024年から2025年にかけて、Sorobanと呼ばれるスマートコントラクト機能の導入を本格化させています。
もともとステラルーメンは送金に特化した設計であり、複雑なプログラムを実行するスマートコントラクトには対応していませんでした。
しかし、Sorobanが実装されることにより、分散型金融(DeFi)やNFTといった幅広い領域での活用が期待されています。
実際に、Sorobanのアップデート後は開発者向けのプラットフォームが充実し、多種多様なdApp(分散型アプリケーション)が登場し始めています。
DeFiの分野では、ステラルーメン上でステーブルコインを用いた貸し借りや自動マーケットメーカー(AMM)のサービスを展開するプロジェクトが増えてきたと報じられています。
処理速度が速く、手数料が安いというステラルーメンの特性は、DeFiにとっても魅力的な要素といえそうです。
参考:Coindesk
最近の注目トピック・提携・導入事例
2025年の年初には、国連開発計画(UNDP)とステラルーメン開発財団がパートナーシップを締結しました。
開発途上国における金融インフラ整備やブロックチェーン技術の社会的応用を促進するための協力関係とされ、国際機関がステラルーメンと組むことで大規模な実証プロジェクトが進む可能性があると注目を集めました。
同じくMastercardとの協業が発表されたことも大きな話題になっています。
Mastercardは世界中でクレジット決済ネットワークを提供する企業であり、その基盤とステラルーメンネットワークが連動することで、新たなデジタル決済サービスを生み出す余地があるといわれています。
さらに、各国政府や銀行もCBDC(中央銀行デジタル通貨)や法定通貨連動ステーブルコインの発行を検討しており、ステラルーメンのような高い処理能力を持つチェーンは候補に挙がりやすいと報道されています。
これらの動きが活性化すれば、実需要の増加によってXLMの取引も活発化するかもしれません。
ステラルーメン/XLMの過去にあった事件・トラブル
- インフレーションバグによる不正発行事件
- ネットワークの一時停止事故
- それぞれの問題を受けた対策や教訓
インフレーションバグ事件
ステラルーメンの歴史の中で最も重大といわれるトラブルの一つが、2017年頃に起きたインフレーションバグ事件です。
当時のコード上の欠陥を悪用され、結果として大量のXLMが不正に発行されるという問題が発生しました。
この影響で、正規の発行上限を超えるXLMが市場に流出してしまった可能性があり、コミュニティからは懸念の声が上がりました。
この事態を受けてステラルーメン開発財団は、直ちにバグの修正を行い、不正に発行された量と同等のXLMを焼却(バーン)する処置を取りました。
ただし、不正発行の事実や対応策を公表するタイミングが遅れたと指摘されることもあり、当時は十分な透明性が確保されていなかったと批判を受けています。
その後、SDFは公開プロセスを見直し、重大なバグやインシデントに対しては速やかに情報を共有する方針を打ち出しました。
ネットワーク停止事故
2019年にはステラルーメンネットワークが約2時間程度にわたり停止する事故が起きました。
この停止は、SDFが運営する主要ノードに信頼が集中していたことで一部ノード障害が連鎖的に広がり、トランザクション処理が進まなくなる状況を引き起こしたといわれています。
この事件は「ステラルーメンは本当に分散化されているのか」という根本的な疑問を投げかけるきっかけにもなりました。
以降、SDFはバリデータの分散化を推進し、多数の独立ノードが参加できるようネットワーク設計を見直しました。
事故以降は大規模な停止は発生していないため、一定の改善効果があったと考えられます。
しかし、PoW系のブロックチェーンと比べてSCPの分散度合いはどうなのか、といった議論は残っています。
こうした議論を通じてプロジェクトの透明性と信頼性が高まっていくことに期待する声もあるため、今後の動向に注目です。
ステラルーメン/XLMの価格動向と将来性
- 過去にはRipple(XRP)のトラブル時に代替通貨として注目された時期がある
- 時価総額は常に上位に位置し、機関投資家からの関心も高い
- Sorobanを軸にしたDeFi展開や金融機関との連携強化に期待
過去の価格推移と市場評価
ステラルーメン/XLMは大きく注目を浴びる前から、時価総額ランキングで20位前後に入るなど一定の存在感を誇っていました。
特に2020年末から2021年にかけて、リップル社が米国証券取引委員会(SEC)から訴訟を受けた際には、「XRPの代替としてXLMが使われるかもしれない」との見方が広がり、短期間で価格が上昇した時期もありました。
もちろんその後の市場環境や規制の動向によって上下を繰り返し、必ずしも一方向的に上がり続けてきたわけではありません。
それでも、ステラルーメンは大手金融機関や国際機関との連携実績が多く、比較的安定した市場評価を得ている印象があります。
仮に大規模な送金プロジェクトでXLMがブリッジ通貨として使われるようになると、取引量が増える可能性はあるかもしれません。
とはいえ、価格は投資家のセンチメントや国際的な規制の動向にも左右されるため、注意が必要です。
ステラルーメン/XLMの今後の展望
今後の展望として特に注目されているのは、Sorobanを軸としたDeFi・Web3ビジネスへの拡張です。
高速かつ低手数料のチェーン上でスマートコントラクトを利用できるようになれば、イーサリアムなど既存のプラットフォームに対して競争力を発揮するかもしれません。
専門家の中には「決済とDeFiの親和性がさらに高まると、金融機関や個人投資家にとって魅力が増す」という見解を持つ人もいます。
また、金融機関や大企業との連携が進むほど、ステラルーメンの信用度や実用性は上がると考えられます。
UNDPやMastercardといった国際的な組織との協力関係は、その一端を示すものです。
さらに、中央銀行デジタル通貨(CBDC)のプラットフォームとしてステラルーメンが採用される例が増えれば、国際送金や金融アクセスのハードルが一段と下がる可能性もあります。
競合チェーンとの比較では、リップル(XRP)やAlgorandなどもクロスボーダー送金や金融向けを強化しているため、一概にステラルーメンだけが優位を独占できるというわけではありません。
ただし、非営利財団による運営姿勢や、すでに築いた企業・団体とのネットワーク効果を活かし、強みを活かした差別化が図れるのではないかという期待もあるようです。
ステラルーメン/XLMとは まとめ
ステラルーメン/XLMは国際送金と金融包摂の分野で成長してきた仮想通貨・ブロックチェーンプロジェクトであり、大手企業や国際機関との提携によりその存在感を高めてきました。
高速決済を可能にするStellarコンセンサスプロトコル(SCP)を採用し、ルーメン(XLM)をネットワーク手数料やブリッジ通貨として活用している点が特徴です。
SorobanアップデートによってDeFiやNFTなどのスマートコントラクト領域にも本格的に参入しており、技術面でも今後の発展が期待されています。
金融機関や国際機関との協働がさらに拡大すれば、ステラルーメンはグローバル決済インフラの一翼を担う存在になるかもしれません。
今後は新しいユースケースやさらなる実需の獲得が、市場評価に大きく影響することになりそうです。自分に合った投資やサービス活用をするためにも、最新の動向をウォッチしてみてはいかがでしょうか。