
パイネットワーク(PI)とは?仕組みや特徴を将来性とともにわかりやすく解説!
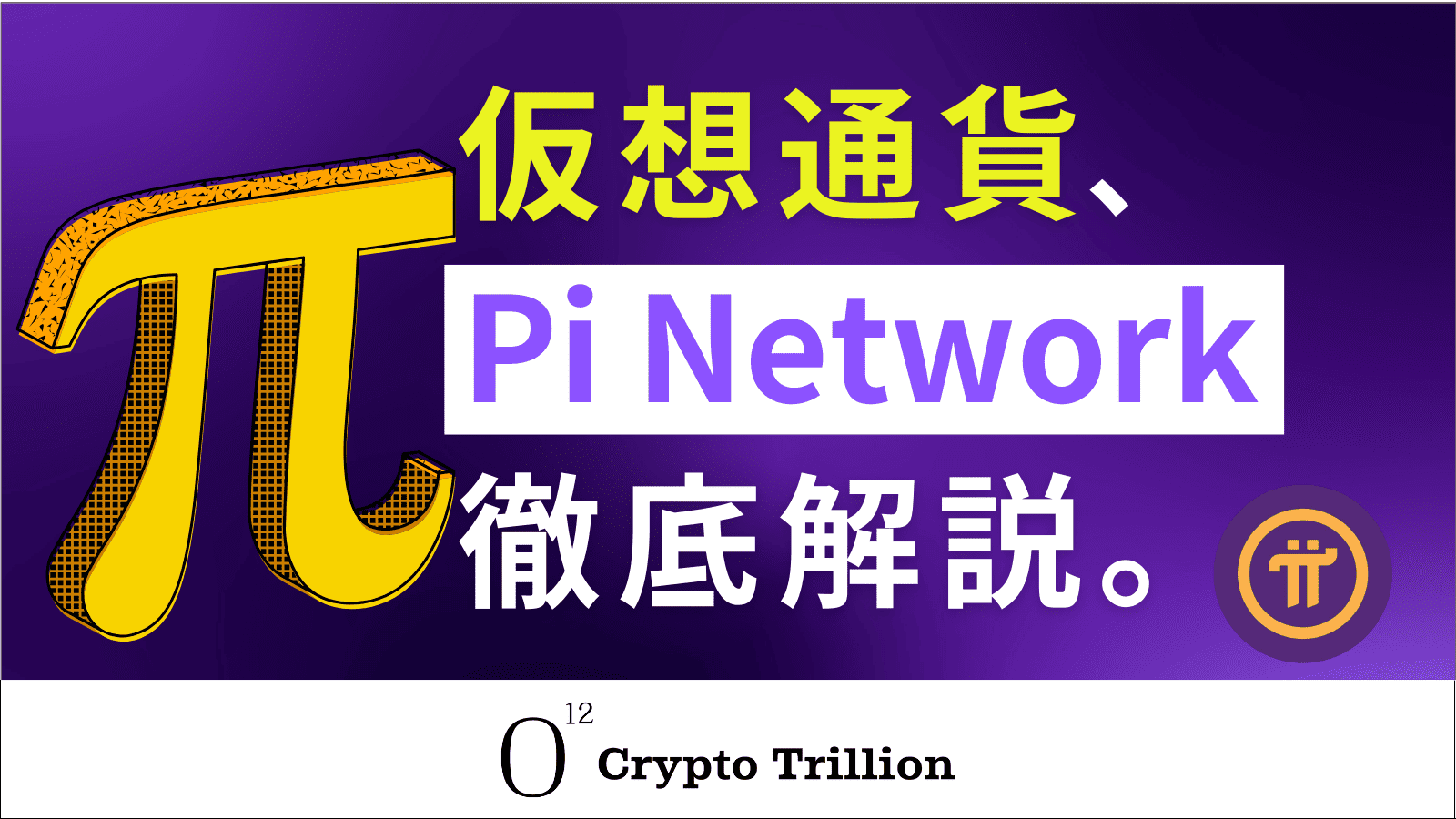
プロトレーダー 木田陽介のイチ押しポイント!
- パイネットワーク(PI)とはスマホで数回タップするだけでマイニングができる仮想通貨
- 今まで大量の電力を消費していたマイニングを、スマホ一つで手軽にできるようになった
- パイネットワークのマイニングはスマホのバッテリーを激しく消耗しない
- パイネットワーク(PI)はどちらかというと中央集権寄りの仕組みになっている
- マイニングしたPIを引き出すにはKYCが必要
- このマイニングは、信頼できる知人を招待してお互いに検証しあうため、ピラミッドスキームが心配される
- パイネットワーク(PI)は現在国内取引所で取り扱っているところはない
- PIは海外取引所のBitgetやMEXC、LBankなどで取り扱われている
- 海外取引所でPIを購入したい場合はGMOコインからの送金がおすすめ
 木田 陽介
木田 陽介パイネットワーク(PI)はスマホで数タップするだけでバッテリーを多く消費せず、マイニングができる仮想通貨プロジェクトです。



ただ、若干中央集権型の気質があるため、これからの動向としては招待制やKYCの別の形や新たな仕組みが出てくることが考えられます。
そうすることで、ピラミッドスキームを連想させることなく、ユーザーからの信頼度も上がって価格にも影響が出てくる可能性があると思います!


木田陽介
GFA WEB3アドバイザー
2016年から仮想通貨トレードを開始。2017年に株式会社CoinOtakuを共同で創業。同年CoinOtakuの代表に就任。2020年に東証二部上場企業のビートホールディングスに6億円でM&Aをし、同企業にて2020年10月〜12月の3ヶ月間で仮想通貨運用益2500万円を達成する。現在はCoinOtaku代表を退任し、GFA株式会社のWEB3アドバイザーに就任。


監修 木田 陽介
GFA WEB3アドバイザー
2016年仮想通貨トレード開始。2017年株式会社CoinOtaku共同創業。同年CoinOtakuの代表に就任。2020年に東証二部上場企業のビートホールディングスに6億円でM&Aをし、同企業にて2020年10月〜12月の3ヶ月間で仮想通貨運用益2500万円を達成する。現在はCoinOtaku代表を退任し、GFA株式会社のWEB3アドバイザーに就任。
パイネットワーク(Pi)とは?
- スマホだけで仮想通貨を「マイニング」できる革新的なプロジェクト
- ユーザー数は数千万人規模ともいわれ、世界的に注目されている
- 操作がシンプルな一方で、実際の価値がどうなるかはまだ未知数
パイネットワーク(Pi)の概要
パイネットワーク(Pi)は、スタンフォード大学出身の開発チームが立ち上げた仮想通貨プロジェクトです。
2019年にローンチしてからスマートフォンで手軽にコインを獲得できる仕組みが話題になり、すぐに世界的な注目を集めました。
公式アプリをスマホへインストールし、1日1回程度アプリ内のボタンをタップするだけで暗号資産のマイニングが続く設計になっているため、従来の仮想通貨マイニングに必要だった高性能PCや多額の初期投資が要りません。
ただし、現在はメインネットがオープン化されたばかりで、外部取引所での価格形成が始まった段階です。
プロジェクトとしてはコミュニティを中心に日常生活でも使える通貨を目指しているため、単に値上がりを期待するだけでなく、実用的な使い道を整備できるかが将来的な課題になりそうです。
誕生の背景とスマホマイニングのアイデア
パイネットワーク(Pi)は「誰でも仮想通貨に触れられる環境を作る」というコンセプトから生まれました。
ビットコインなどの従来型マイニングは多大な電力を消費するうえに複雑な設定が必要で、新興国や一般ユーザーには参加しづらい面がありました。
そこでスマホひとつで仮想通貨に参加できるシステムを導入し、さらに紹介制度を設けてユーザーが友人や家族を招待し合う形でコミュニティを拡大しています。
技術的にはStellar Consensus Protocolを基盤とし、ユーザー同士の信頼関係をネットワーク保護に活用する点が革新的だといわれています。
パイネットワーク(Pi)の特徴
- スマホアプリでのマイニングにより省エネを実現
- ユーザー間のセキュリティサークルで不正を防止
- KYCによる身元確認を重視し、健全なコミュニティ作りを目指す
モバイルマイニングと省エネ設計
スマホでボタンをタップするだけという簡単な操作が特徴です。
ビットコインのように膨大な電力を要するマイニングではなく、Stellar Consensus Protocolを改良した仕組みにより、端末に負荷をかけずにトランザクションを検証できるよう設計されています。
バッテリーを激しく消耗しない点もユーザーへの配慮といえます。
この方法を採用したことで、ブロックチェーン関連の知識や高性能パソコンが必要ないため、新興国やITリテラシーの低い方でも参加しやすい環境を整えているようです。
ただし、無料であるがゆえに「本当に価値が生まれるのか」という疑問の声も根強くあります。
セキュリティサークルとコミュニティ構築
パイネットワーク(Pi)では「セキュリティサークル」と呼ばれる仕組みを導入しています。
ユーザーは自身が信用できる知人をサークルに追加し合い、互いに検証し合うことで不正防止に努めています。
さらに、KYC(本人確認)を行わないと最終的に獲得したコインを引き出せないルールがあるため、一人で複数のアカウントを作って不正に報酬を得る可能性を下げているようです。
招待制を採用していることも大きな特徴です。
既存ユーザーからのコードがなければ登録できない仕組みで、招待者と被招待者の両方にマイニング速度のボーナスが付与されます。
結果として口コミやSNSを通じ、短期間で爆発的なユーザー拡大につながりました。
パイネットワーク(Pi)が注目を集めた理由
- 無料で始められるという手軽さが大きな魅力
- 爆発的なユーザー数と賛否両論の議論が広まり、話題性を獲得
- 将来への期待感から多くのコミュニティメンバーが参加を継続
無料かつ手軽に始められる魅力
パイネットワーク(Pi)はスマホアプリをインストールして毎日ボタンを押すだけというシンプルさを武器に、急速にユーザー数を増やしています。
しかも登録や利用に費用がかからないため、多くの初心者にとってハードルが非常に低いといえます。
こうした気軽さから「試してみるだけなら損はない」と感じる人が多いようです。
このようにユーザーが多ければ多いほど、コミュニティやエコシステムが発展しやすいのもメリットと考えられます。
たとえ個人が短期間で大きな利益を得られないとしても、参加者全体が協力して利用シーンを増やせば、長い目で見れば通貨価値が育つかもしれません。
爆発的ユーザー数とメディア報道
世界規模でユーザーが何千万人を超えているともいわれ、メディアでも「新手の仮想通貨」として度々取り上げられてきました。
SNSではポジティブな意見だけでなく、「マルチ商法ではないか」「実際に換金できるのか」といった疑問の声も目立ちます。
こうした論争や批判が逆に話題性を広げた一因となり、結果としてパイネットワーク(Pi)の知名度が高まりました。
招待制によりユーザー同士が積極的に勧誘を行ってきた点もコミュニティ拡大を後押ししたようです。
Piと他の仮想通貨との決定的な違い
- 大規模な計算処理を必要としないため、初心者でも参加しやすい
- 運営主体が明確で、KYCを含む中央集権的な要素が強い
- 日常生活で使えるピアツーピア通貨を目指す点がビットコインなどと異なる
ビットコインやイーサリアムとの比較
ビットコインは大量の電力を消費するマイニングが課題となり、イーサリアムも現在はステーク方式に移行していますが、Validatorとして活動するにはまとまった量のETHを預ける必要があります。
パイネットワーク(Pi)はそのどちらとも異なり、スマホアプリで省エネかつ無料で始められる点が大きいといわれています。
また、ビットコインは完全な分散型通貨として確立されており、特定の管理者が存在しません。
パイネットワーク(Pi)はスタートアップ企業がプロジェクトを主導する形を取っているため、ある程度の中央管理体制を兼ね備えている印象があります。
使用目的・エコシステムの方向性
ビットコインがデジタルゴールドとして注目され、イーサリアムがスマートコントラクトの基盤として発展してきたのに対し、パイネットワーク(Pi)は日常生活で使うことを目指すP2P(ピアツーピア)通貨としての価値創造に注力しているようです。
KYCによって実在する人物しか参加できない設計のため、支払い手段や商取引の安全性を確保しやすいという見方もあります。
しかし、この点を逆に「匿名性が薄れてしまう」と考えるユーザーもいるため、どのような形で広く受け入れられるかはまだ未知数でしょう。
パイネットワーク(Pi)の今後・将来性
- オープンメインネットへの移行により外部取引所での価格形成が進行中
- エコシステム拡大と利用シーンの確立が通貨価値に影響する可能性あり
- ピラミッドスキーム疑惑を払拭できるかが長期発展のカギ
メインネット移行の影響
2025年にオープンメインネットへ移行したことで、獲得したPiコインを外部のウォレットに移せるようになりました。
主要な取引所に上場し始めていることから、徐々に市場価格が形成されつつあるようです。
正式な価値がついたことで一般的な暗号資産に近づきましたが、取引量や流動性の面ではまだ拡大の余地がありそうです。
今後はさらに大手取引所に上場し、幅広い投資家の目に留まることになれば、価格が上下に動く可能性が高まります。
一方で、実際の利用シーンが増えず投機目的ばかりが先行すると、プロジェクトの本来の目的が霞んでしまうかもしれません。
専門家の見方と残る課題
パイネットワーク(Pi)はユーザー基盤の大きさや斬新な仕組みで一定の評価を得ていますが、専門家の間では「今後どれだけ実需を生み出せるか」が焦点とされています。
たとえばPiコインを使った決済サービスが普及すれば、プロジェクトの知名度だけでなく実際の通貨価値も安定する可能性があります。
しかし、紹介制度がピラミッドスキームに近い形を連想させると指摘されることも少なくありません。
KYC情報の取り扱いについても懸念を示す声があるため、開発チームがこうしたリスクへの対策を明確に示すことが長期的な発展につながるでしょう。
今までのWeb2と、同じような構造にならない仕掛けを作る必要はありそうです。
パイネットワーク(Pi)ニュース・動向
- 2025年2~3月にかけてメインネットがオープンし、取引所上場が進む
- Pi Day(3月14日)のイベントで今後のロードマップが発表された
- コミュニティでは商取引の実用例が増え始めている
2025年2〜3月の主要トピック
2月下旬のオープンメインネット開始により、長らくアプリ内で閉じられていたコインが実際に外部ウォレットへ送金できるようになりました。
同時にOKXやBitgetなどの取引所で取り扱いがスタートし、初値は1~2ドル台で推移していると報じられています。
取引ボリュームも一定以上の数字を示しており、コミュニティにおける期待の大きさをうかがわせます。
3月14日は「π(パイ)」にちなみ、パイネットワーク(Pi)にとって毎年恒例の記念日です。
今年はメインネット解放直後だったこともあり、今後予定されているエコシステム構築や新機能のロードマップに関する情報が公式から公開されました。
コミュニティの最新動向
SNSでは商店やオンラインサービスがPiコインによる決済を試験的に導入しているという報告が増えているようです。
メインネット公開直後は不慣れなユーザーも多かったため、ウォレット移行やKYCをめぐるトラブルが散見されましたが、最近は運営がサポート体制を強化していると案内しています。
今後はハッカソンなどのイベントを通じ、さらなるアプリケーションやサービス開発が活性化するかもしれません。
パイネットワーク(Pi)まとめ
パイネットワーク(Pi)は、スマホのみで手軽に暗号資産を獲得できることから一気に広がり、多数の参加者を抱えるプロジェクトに成長しました。
簡単にマイニングできる仕組みやユーザー同士のセキュリティサークルなど、既存の仮想通貨にはない面白さがある一方で、まだ懐疑的な見方が拭えない部分も残っています。
オープンメインネット移行を経て正式な市場評価が始まった今、パイネットワーク(Pi)は実社会での使い道を広げることが重要になるでしょう。
これから始める場合には、まずは公式サイトやSNSの情報をこまめにチェックし、コミュニティでのやり取りをよく確認したうえで判断することが大切です。
無料で参加できるメリットがある一方で、必ずしも大きな利益につながるとは限らないため、慎重に情報収集を続けながら動向を見守る姿勢が望ましいでしょう。

